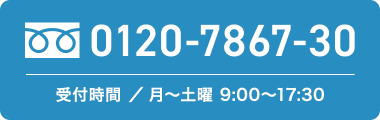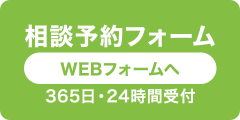交通事故問題の解決期限

監修者: 交通事故チーム主任弁護士
羽賀 倫樹 (はが ともき)
交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。
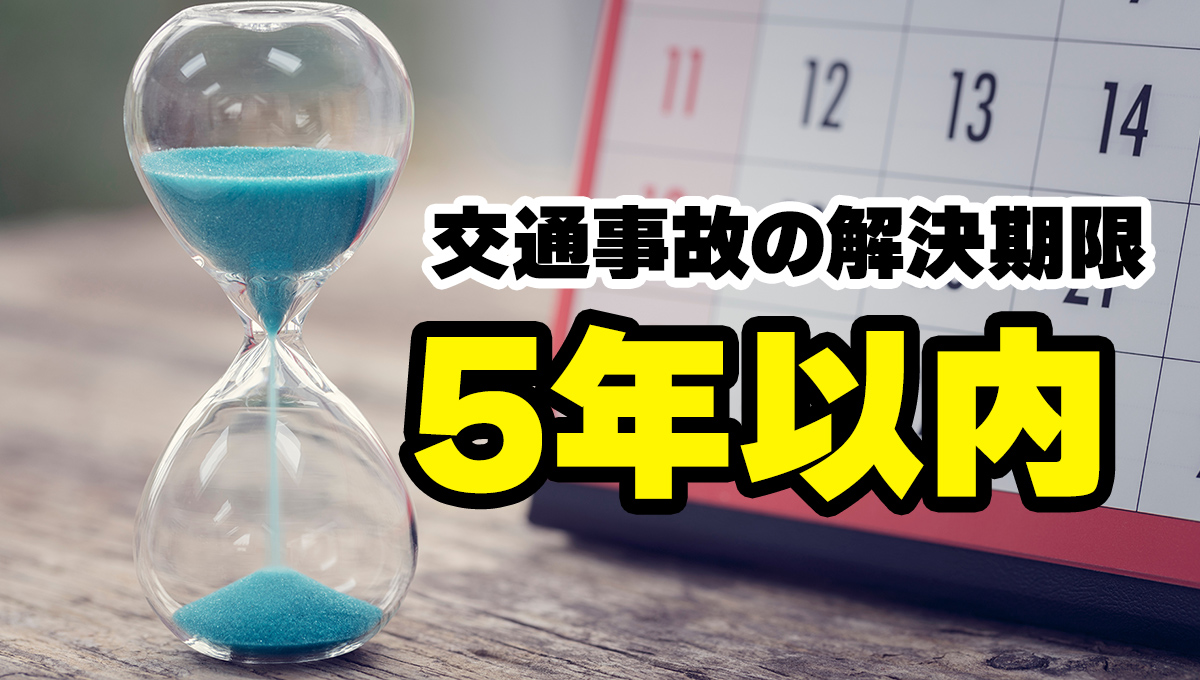
- 相談者
- 交通事故に遭ったんですが、いつまでに解決しないといけないんでしょうか?
- 羽賀弁護士
- 人損部分と物損部分で期限は異なります。人損部分は5年、物損部分は3年が時効期間になります。
状況によって期間が延びることがありますので、一緒に具体的なケースを見ていきましょう。
- この記事でわかること
-
- 交通事故で怪我をして後遺障害が残った場合の解決期限について
- 交通事故で怪我をしたものの後遺障害は残らなかった場合の解決期限について
- 交通事故で発生した物損の解決期限について
- 交通事故で人損と物損の両方が発生した場合の解決期限について
- こんな方が対象の記事です
-
- 交通事故に遭遇し、解決期限や時効について詳しく知りたい方
- 人損事故と物損事故の解決期限について知りたい方
- 後遺障害が残った場合と後遺障害が残らなかった場合の解決期限について知りたい方
- 交通事故で人損と物損の両方が発生した場合の解決期限について知りたい方
交通事故の被害に遭った場合、最終的に保険会社との示談交渉等で解決に至りますが、解決には期限があります。法的には、消滅時効の問題となり、物損は3年以内に、人損は5年以内に解決する必要があります。ここでは、発生した損害内容別に、どの時点から3年または5年で解決する必要があるのか等について見ていきたいと思います。
なお、消滅時効の問題を定める民法の改正との関係で、ここでは2017年4月1日以降に発生した交通事故を対象にします。2017年3月31日以前に発生した交通事故の場合、人損についても3年以内の解決が必要になる場合があります。
交通事故で怪我をして後遺障害が残った場合
症状固定時点から5年で解決する必要があります。ただし、多くの場合、症状固定後に保険会社から最終の治療費が支払われ、示談額の提案がされます。この場合は、治療費の支払い時点や示談額の提案時点から5年以内に解決すればよいことになりますが、事故から20年経過すると時効になります。
交通事故で怪我をしたものの後遺障害は残らなかった場合
事故時または症状固定時(治癒時)から5年で解決する必要があります。ただし、後遺障害が残らない場合も、多くの場合、症状固定後(治癒後)に保険会社から最終の治療費が支払われ、示談額の提案がされます。この場合は、治療費の支払い時点や示談額の提案時点から5年以内に解決すればよいことになりますが、事故から20年経過すると時効になります。
交通事故で発生した物損
事故時から3年で解決する必要があります。事故後に保険会社から物損示談額の提案があった場合は、示談額の提案時点から3年以内に解決すればよいことになりますが、事故から20年経過すると時効になります。
交通事故で人損と物損の両方が発生した場合
この場合は、人損は5年、物損は3年で解決する必要があります。人損と物損で解決期限が異なるため、注意が必要です。
交通事故で人損と物損の両方が発生した場合、人損と物損の消滅時効期間が異なることについては、以下の最高裁判所判決があります(読みやすくするために、最高裁判所の原文に一部改変を加えています)。
最高裁判所令和3年11月2日第三小法廷判決(民集 第75巻9号3643頁)
「交通事故の被害者の加害者に対する車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権(物損)の短期消滅時効は、同一の交通事故により同一の被害者に身体傷害を理由とする損害(人損)が生じた場合であっても、被害者が、加害者に加え、上記車両損傷を理由とする損害を知った時から進行するものと解するのが相当である。
なぜなら、車両損傷を理由とする損害(物損)と身体傷害を理由とする損害(人損)とは、これらが同一の交通事故により同一の被害者に生じたものであっても、被侵害利益を異にするものであり、車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権(物損)は、身体傷害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権(人損)とは異なる請求権であると解されるのであって、そうである以上、上記各損害賠償請求権(物損と人損)の短期消滅時効の起算点は、請求権ごとに各別に判断されるべきものであるからである。」
まとめ

なお、消滅時効の起算点の結論については、法律に明確に書かれているわけではなく、一般的にそのように扱われているという趣旨です。異なる判断をしている裁判例がないわけではないので、注意が必要です。
3年または5年というととても長い期間のように思われるかもしれません。しかし、手続きを置いていたり、多くの手続きを重ねていると、3年または5年という期間は意外とすぐに過ぎてしまう場合があります。どの時点で時効となるかが争いとなる事案もありますし、弁護士としても、時効ギリギリの事案は受けられない場合があります。時効の問題を避けるには、テンポよく手続きを進めていくことが最も重要です。
更新日:2020年9月21日

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

示談金増額を目指します


ご相談者様への
お約束
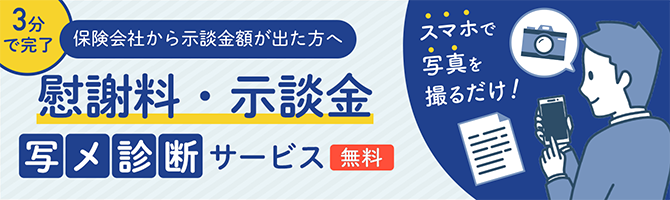
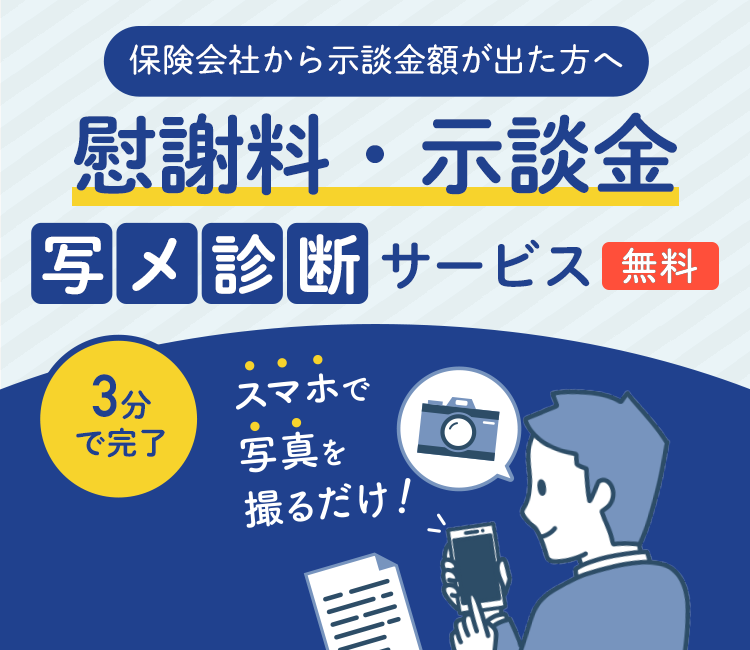


交通事故直後から知っておきたいこと の記事一覧
- 事故直後に行うべき手続き
- 適正な慰謝料請求のための手続きの進め方と実況見分立会いの重要性
- 警察による実況見分と供述調書の説明と対応のポイント
- 警察における人身事故と物件事故の違い
- 交通事故の治療は「保険診療」と「自由診療」のどちらで受けるべき?
- 整形外科と整骨院の選択
- 交通事故ではいつまで治療費が支払われる?
- 賠償金支払いの仕組みと、加害者・被害者・保険会社の関係について。
- 交通事故問題の解決に関わる方々と、利害関係について。
- 交通事故問題の解決期限
- 交通事故を弁護士に依頼するタイミングとメリット
- 後遺障害等級別の弁護士依頼のタイミングの傾向
- 交通事故の弁護士費用特約の活用方法
- 交通事故の手続きを弁護士に依頼する場合の弁護士費用
増額しなければ
弁護士費用はいただきません!
※弁護士特約の利用がない場合