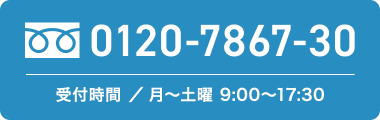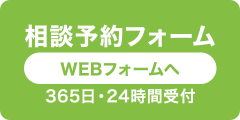後遺障害逸失利益の基礎収入

監修者: 交通事故チーム主任弁護士
羽賀 倫樹 (はが ともき)
交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

- 相談者
- 交通事故で怪我をし、後遺障害が残ってしまいました。
後遺障害逸失利益の計算で用いられる、基礎となる収入(基礎収入)はどのように算出されるのでしょうか?
- 羽賀弁護士
- 事故時の職業によって変わることがありますが、基礎収入を算定するのは容易でないこともありますので、弁護士に相談されるのをお勧めしています。
- この記事でわかること
-
- 給与所得者(会社員)の基礎収入の算定方法
- 家事従事者(主婦)の基礎収入の算出方法
- 幼児・児童・学生の基礎収入の考え方
- 無職の場合の基礎収入の考え方
- こんな方が対象の記事です
-
- 交通事故で後遺障害が残った方やその家族の方
- 後遺障害逸失利益の基礎収入の算出方法を知りたい方
- 給与所得者の後遺障害逸失利益の基礎収入の算出方法を知りたい方
- 家事従事者(主婦)の後遺障害逸失利益の基礎収入の算出方法を知りたい方
- 幼児・児童・学生の後遺障害逸失利益の基礎収入の算出方法を知りたい方
- 無職の場合の後遺障害逸失利益の基礎収入について知りたい方
はじめに
交通事故で怪我をし、後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害逸失利益の補償を受けることができます。逸失利益は、基礎となる収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間の計算式で算出されますが、ここでは、基礎となる収入(基礎収入)がどのように算出されるか、交通事故前の職業別に見ていきたいと思います。
給与所得者(会社員)の場合
概ね30才以上の場合

交通事故の前の年の年収が基礎収入になります。会社員や公務員であれば、源泉徴収票記載の金額が基礎収入になります。
ただ、事故の前の年の年収が高い場合でも、定年等により給与の減額が見込まれる場合は、定年後は基礎収入を下げて計算することがあります。例えば、事故前50才で1000万円の年収があったものの、60才以降は定年後の再雇用になり、年収が半分以下になることが見込まれるような場合は、60才までは基礎収入は1000万円、60才以降は400万円といった形で計算されます。
概ね30才未満の場合

性別ごとの平均賃金や、さらに学歴を加味した平均賃金を用いることが多くあります。また、交通事故の前の年の年収と、学歴年齢別の平均賃金や男女年齢別の平均賃金を対比して基礎収入を算定することも多くあります。
例えば、高卒27才男性の方で交通事故の前の年の収入が370万円という場合、男性の平均賃金約550万円や、高卒男性の平均賃金約480万円を基礎収入とすることがよくあります。
保険会社が被害者の方自身に示談提示をするときは、交通事故の前の年の収入を基礎収入としていることがあり、注意が必要です。
家事従事者(主婦)の場合

女性の平均賃金が基礎収入になります。
家事従事者というのは、自分以外の誰かのために家事を行っている方を意味しており、一人暮らし主婦の方は、逸失利益の算定上、家事従事者ではなく無職者となります。
仕事もしているという場合は、実収入と女性の平均賃金の高い方を基礎収入とします。
60才以上の方の場合、女性の年齢別の平均賃金を基礎収入とすることがあります。さらに高齢の方の場合、女性の年齢別の平均賃金から減らした金額を基礎収入とすることや、健康状態等によっては家事従事者としての認定が受けられず基礎収入が0円になることがあります。
保険会社が被害者の方自身に示談提示をするときは、女性の平均賃金より低い額を基礎収入としていることがあり、注意が必要です。
幼児・児童・学生の場合

性別ごとの平均賃金を用いることが多いと言えます。男性は男性の平均賃金、女性は女性の平均賃金を基本としますが、女性で年少と言い得る場合(高校生程度まで)は、男女の平均賃金を用いることが多いと言えます。また、大学院や大学の卒業が見込まれる場合は、大学卒男女別の平均賃金を用いることが多いと言えます。
保険会社が被害者の方自身に示談提示をするときは、20才~24才の平均賃金を用いるなど、低い額を基礎収入としていることがあり、注意が必要です。
無職の場合

無職の場合は、そもそも逸失利益が認められなくてもやむを得ないところがありますが、年齢・職歴・能力・意欲などを考慮して、就職の蓋然性があれば、逸失利益が認められます。逸失利益が認められる場合の基礎収入は、年齢や失業前の収入を考慮して定められますが、やや低い金額を基礎収入とすることが多いと言えます。
まとめ

以上職業別に基礎収入の考え方を見てきましたが、以上の記載以外にも例外的な場合は多くあり、基礎収入を定めるのが容易でないことはよくあります。保険会社は、基礎収入の点以外でも示談金の支払いを減額しようとしてくることがよくありますので、保険会社から示談額が提示された時は、弁護士に相談するのがいいでしょう。
更新日:2019年7月12日

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

示談金増額を目指します


ご相談者様への
お約束
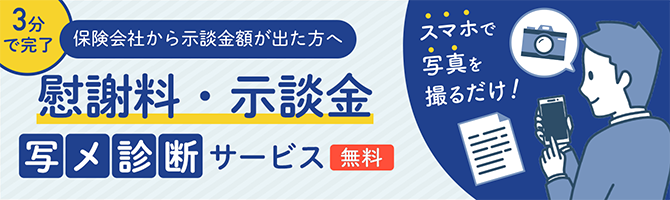
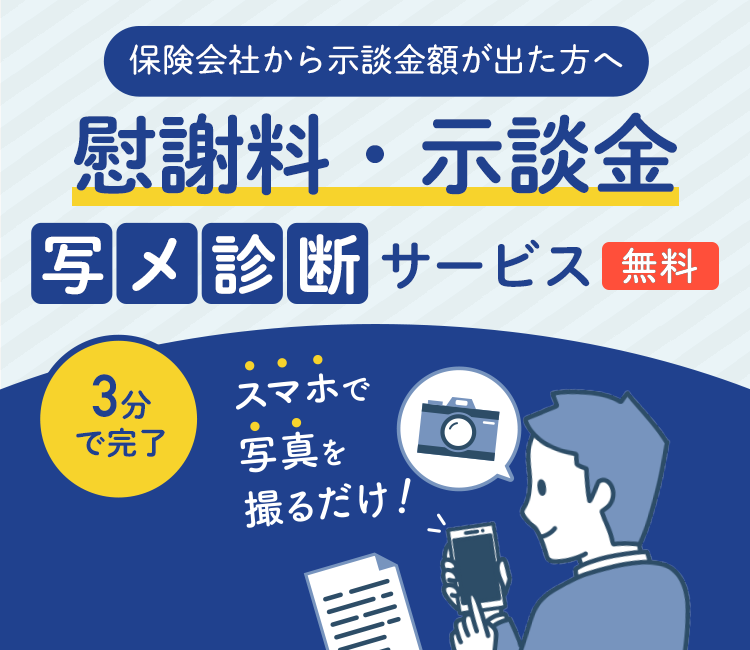


増額しなければ
弁護士費用はいただきません!
※弁護士特約の利用がない場合