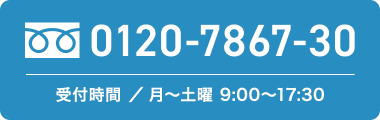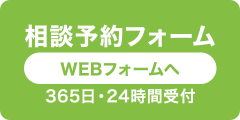交通事故問題の解決に関わる方々と、利害関係について。

監修者: 交通事故チーム主任弁護士
羽賀 倫樹 (はが ともき)
交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

- 相談者
- 交通事故で怪我をしたら弁護士・医師・保険会社の担当者・警察の人等とどのようにかかわっていけばいいのでしょうか?
- 羽賀弁護士
- 交通事故被害者の方の利益を最優先に考えるのは、主に私たち弁護士とあなたを治療する医師になります。
「公益の代表者」である警察や検察は、必ずしも被害者の「味方」とは言い切れない側面があります。
示談交渉を適切に行うために、それぞれの関係者の利害関係について知っておく必要があります。
この記事では、交通事故問題の解決に関わる方々と、その利害関係について解説します。
- この記事でわかること
-
- 交通事故問題に関わる主な関係者
- 各関係者の利害関係について
- 被害者の利益を最優先に考える関係者とは
- 被害者と利益が対立する可能性がある関係者について
- こんな方が対象の記事です
-
- 交通事故で怪我をしたり、被害に遭った方
- 自分の利益を守るために誰に相談すれば良いか知りたい方
- 交通事故に関わる関係者との利害関係について知りたい方
交通事故問題の関係性
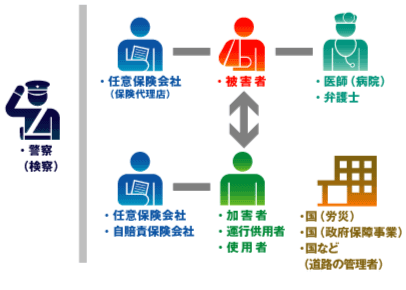
交通事故問題の解決に際しては、様々な人が関係してきます。ここでは、先にご説明した「自動車保険の仕組み」をもとに、もう少し範囲を広げて、交通事故問題に関係しそうな人を示します。
右記の関係図で「被害者の利益」を考えてくれる人は、誰でしょうか。答えは、弁護士と医師となります。ただし、医師は治療費の単価の点で対立する場合も稀にあります。(下記「経験談」を参照ください)
警察や検察はどうなのかと言えば、必ずしも被害者の「味方」とは言い切れません。「公益の代表者」として、少ない人的資源でやりくりする以上、仕方のないことかもしれませんが、「事件を迅速に処理するために、杜撰な事故現場見取図を作成した」と言う話を聞くこともあります。
また、体が動かない被害者から現場説明を受けず、加害者の現場説明だけをもとにして、事故現場見取図を作成して「それでよし」とするのは日常茶飯事です。実際に、示談交渉の場面で、被害者の記憶と異なる見取図がネックとなり、過失割合が不利になることは非常に多くあります。
被害者と加害者の関係性

次に、被害者の利益に反する言動をする可能性がある人は、誰でしょうか。被害者の立場からは「誰にお金(示談金や保険金)を請求できるか」、逆の見方で、「誰が財布を痛めて被害者にお金を支払わねばならないか」という点を考えるとお分かりになると思います。
被害者の利益に反する言動をする可能性があるのは、加害者、運行供用者、加害者の使用者、加害者加入の自賠責保険会社・任意保険会社、被害者加入の任意保険会社(人身傷害保険、無保険車傷害保険等)、国(労災、政府保障事業、道路の管理者)です。上記の表のうちのほとんどが、それに該当します。
国(労災)は、後遺障害等級の認定の時点で、被害者の想定していた等級より低い等級を認定して対立する可能性があります。また、国(政府保障事業)は、ひき逃げの際に保険金を請求することになるため、被害者と対立する可能性があります。さらに、国などの道路の管理者については、「道路に穴が開いていた」といった不備が原因の事故であった場合、被害者は国家賠償を請求することになるため、対立する可能性があります。
もっとも、通常の事故では、加害者の契約する保険会社を念頭に置けば、ほとんどの場合は問題ありません。
保険会社との関係性

上記のように、被害者と加害者加入の保険会社は、敵対関係にあります。被害者の方で、「保険会社は事故の専門家だから、全て正しいことを言ってくれるだろう」と誤解をされている方がいますが、残念ながら違います。
保険会社は、嘘を言うわけではありませんが、「被害者の利益を考えてくれる」というわけでもありません。保険会社も「営利企業」ですので、利益を出すために、「入るを計りて(保険料を支払ってくれる契約者を獲得する)出るを制す(必要経費と被害者に支払う保険金を減らす)」をしないといけないのです。そこで、保険会社は、下記のような内容の連絡をしてくることがあります。
- 最低限の保障に過ぎない自賠責保険の基準を持ち出して、
「基準ではこうなっているので、これくらいの保険金が適正です」 - 「これくらいの怪我なら、半年で症状固定するのが普通なので、治療費や休業補償を打ち切ります」
については、弁護士基準、任意保険会社基準、自賠責保険基準の3つのうちのどれかを言わないところがポイントです。
については、本来、症状固定の判断は医師しかできないにも関わらず、治療費や休業損害の打ち切りを独断で通告してくるのです。
経験談
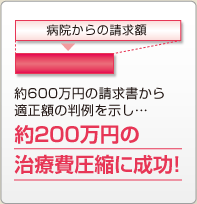
赤信号無視で交差点を横断中に自動車に接触し、意識不明のままA病院に入院し、1か月後に死亡した方がいました。
当事務所は相続人から依頼を受け、証拠書類を集めたところ、A病院から約600万円近くの請求書を受け取りました。被害者側の過失割合が非常に大きいことから、何とかこれを圧縮する必要がありました。
診療報酬明細書(どういう治療をして、その点数がいくらかが書いてある書類)を精査すると、1点単価が15円と、通常の1.5倍で計算されていました。
そこで、意識不明のまま病院に搬送され治療を受けた場合の1点単価の適正額を10円などとする判例(東京地裁平成元年3月14日判決、判例時報1301号21頁)を示して200万円近く治療費を圧縮することができました。
次のページでは、保険会社が賠償金の計算に使う基準値と弁護士が使う基準値の違いを解説しています。
更新日:2016年11月29日

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

示談金増額を目指します


ご相談者様への
お約束
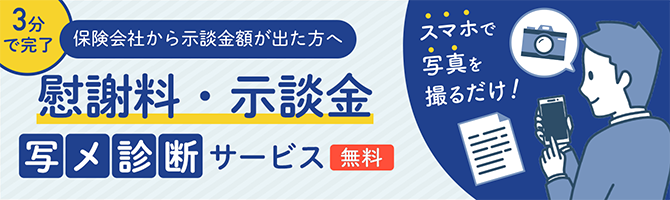
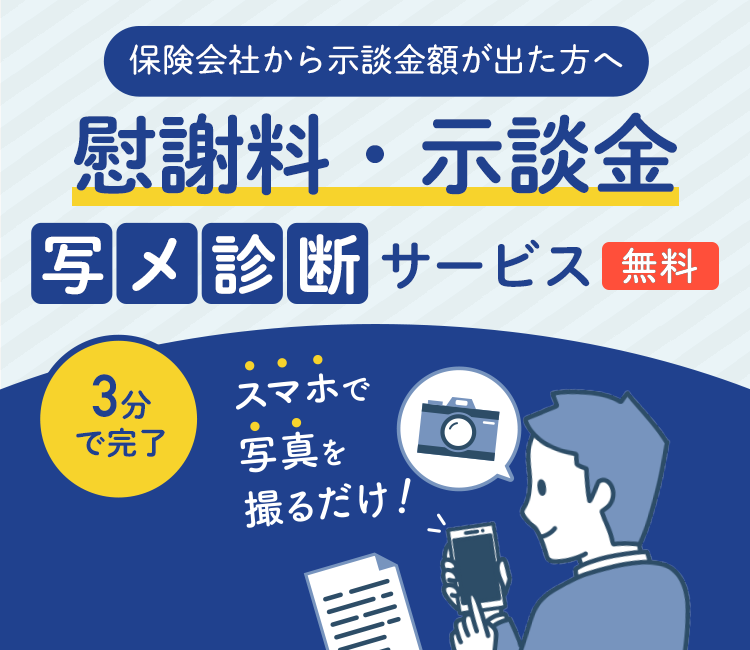


交通事故直後から知っておきたいこと の記事一覧
- 事故直後に行うべき手続き
- 適正な慰謝料請求のための手続きの進め方と実況見分立会いの重要性
- 警察による実況見分と供述調書の説明と対応のポイント
- 警察における人身事故と物件事故の違い
- 交通事故の治療は「保険診療」と「自由診療」のどちらで受けるべき?
- 整形外科と整骨院の選択
- 交通事故ではいつまで治療費が支払われる?
- 賠償金支払いの仕組みと、加害者・被害者・保険会社の関係について。
- 交通事故問題の解決に関わる方々と、利害関係について。
- 交通事故問題の解決期限
- 交通事故を弁護士に依頼するタイミングとメリット
- 後遺障害等級別の弁護士依頼のタイミングの傾向
- 交通事故の弁護士費用特約の活用方法
- 交通事故の手続きを弁護士に依頼する場合の弁護士費用
増額しなければ
弁護士費用はいただきません!
※弁護士特約の利用がない場合