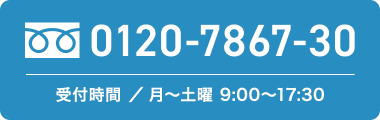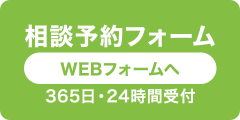後遺障害が残った場合の労働能力喪失期間

監修者: 交通事故チーム主任弁護士
羽賀 倫樹 (はが ともき)
交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。
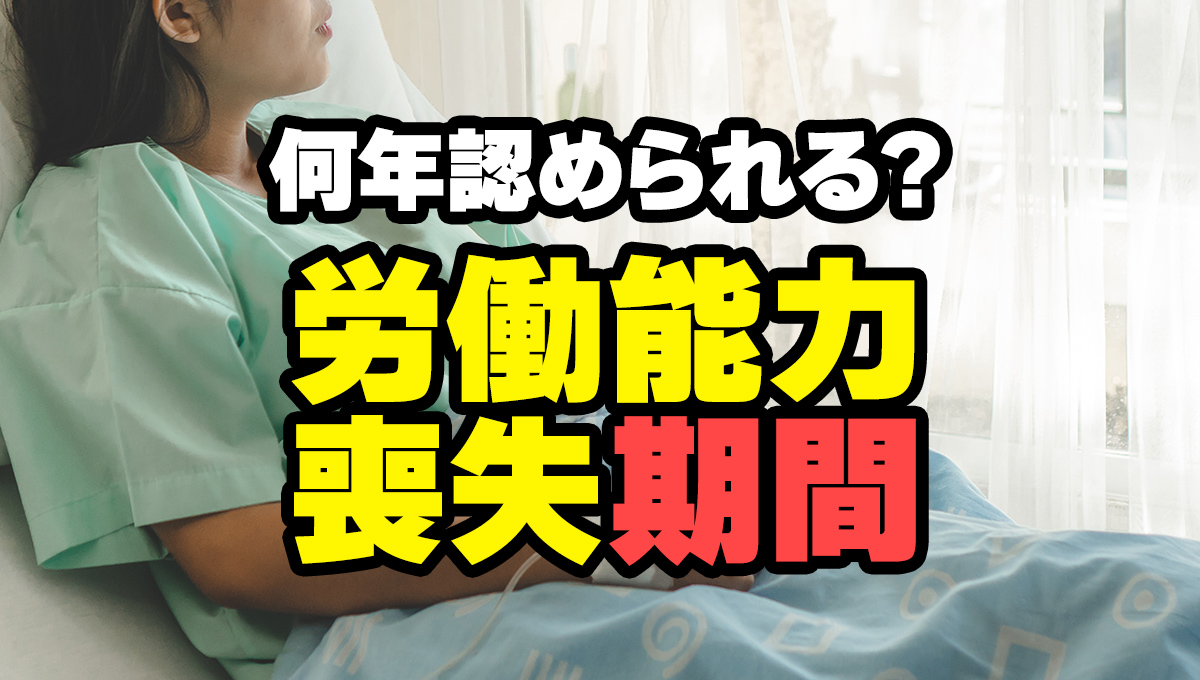
- 相談者
- 交通事故で後遺障害が残り、長い期間働き方に影響が出るかもしれません。
後遺障害がいつまで働き方に影響を及ぼすかは、どのように考えられているのでしょうか?
- 羽賀弁護士
- 後遺障害が残った場合、その後遺障害がいつまで残り、いつまで労働能力に影響を与えるかについて、労働能力喪失期間という概念で表します。
複雑な計算を必要とするので、交通事故を多く扱っている弁護士に相談するのがおすすめです。
- この記事でわかること
-
- 労働能力喪失期間とは何か
- 一般的な労働能力喪失期間の算定基準
- むち打ち症など特定の後遺障害に対する労働能力喪失期間の制限
- 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数について
- こんな方が対象の記事です
-
- 交通事故で後遺障害が残った方やその家族の方
- 労働能力喪失期間の算定方法について知りたい方
- 交通事故による補償で適切な額を受け取りたいと考えている方
- 示談金交渉について弁護士に相談するメリットを知りたい方
労働能力喪失期間とは?

交通事故で後遺障害が残ってしまった場合、労働能力喪失期間という概念が出てきます。これは、後遺障害が残った場合、その後遺障害がいつまで残り、いつまで労働能力に影響を与えるかの期間を示すものです。一般的に、労働能力喪失期間は67才までか、平均余命の2分の1のいずれか長い方とされています。これは、後遺障害は一般的に治らないと考えられることと、一般的に67才までは働くことができるし、ある程度の年齢で働いている人は平均余命の2分の1程度は働くことができるだろうと考えられているからです。
ただ、交通事故で認められる後遺障害のある程度の部分を占めているむち打ちによる後遺障害の場合、労働能力喪失期間は下記のように制限されます。
| 状況 | 年数 |
|---|---|
| むち打ちで14級9号が認定された場合 | 3年~5年 |
| むち打ちで12級13号が認定された場合 | 5年~10年 |
これは、むち打ちの場合、数年単位で期間が経過すると、症状が軽くなる可能性があると考えられているからです。現実には、もっと早く治っている人もいるようですし、ずっと治らないという人もいるようですが、交通事故の手続き上は上記のように取り扱われています。
打撲や捻挫など骨折がない場合で痛みやしびれの症状が残り、14級9号後遺障害が認定された場合も、労働能力喪失期間が3年~5年に制限されることが多いと言えます。また、骨折後に痛みやしびれが残り、14級9号または12級13号の後遺障害が認定された場合も、労働能力喪失期間が制限される事例が多くあります。その他、12級の関節可動域制限が残った場合に、労働能力喪失期間の制限が主張されることがあります。
保険会社との交渉について
以上の他、後遺障害が残ったとしても、徐々にその後遺障害に慣れていき労働能力への影響がなくなるという理由で、保険会社が労働能力喪失期間の制限を主張してくることがあります。
労働能力喪失期間の制限が主張されたときは、それが妥当なものであるかを検討して、少しでも喪失期間を延ばし、示談金を増額できるよう交渉する必要があります。
後遺障害が残った場合
後遺障害が残った場合の逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数で計算されます。ライプニッツ係数という概念の詳細は別のページで説明していますが、労働能力喪失期間の数字そのままをかけるのではなく、それより小さい数字をかけることになります。例えば、下記の通りとなります。
| 労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 (2020年3月31日までの事故の場合) |
ライプニッツ係数 (2020年4月1日以降の事故の場合の一例) 変更になる場合もあります。 |
|---|---|---|
| 5年 | 4.3295 | 4.5797 |
| 10年 | 7.7217 | 8.5302 |
| 20年 | 12.4622 | 14.8775 |
| 30年 | 15.3725 | 19.6004 |
| 40年 | 17.1591 | 23.1148 |
このように、後遺障害が残った場合の逸失利益は、保険会社と争いになることがあり、少し複雑な計算をしないと算出ができないものです。保険会社から出てきた逸失利益の計算が妥当であるかは、交通事故を多く扱っている弁護士に相談してみるといいでしょう。
更新日:2019年7月12日

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

示談金増額を目指します


ご相談者様への
お約束
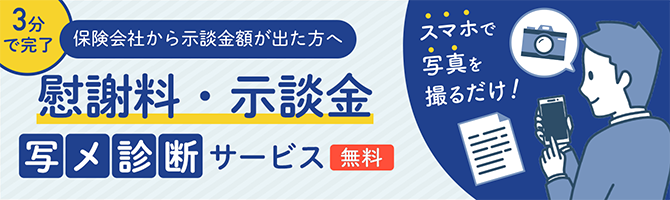
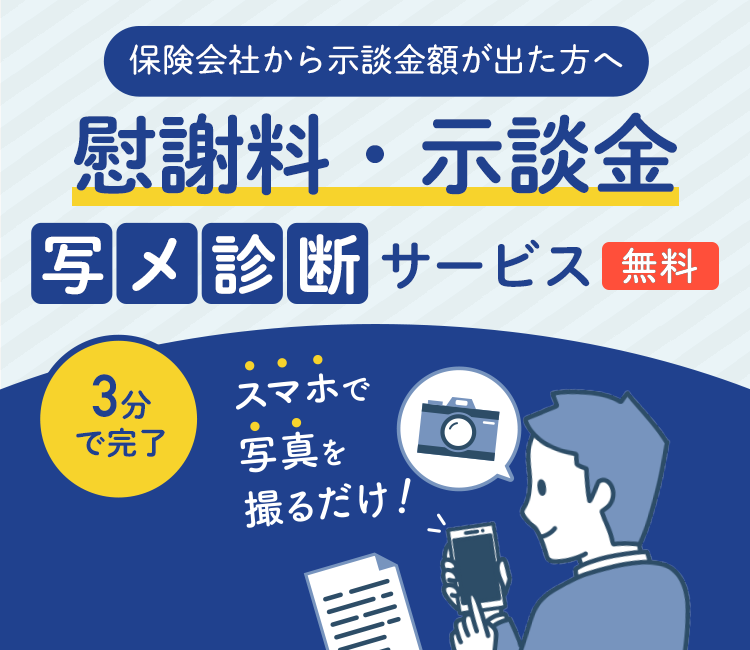


増額しなければ
弁護士費用はいただきません!
※弁護士特約の利用がない場合