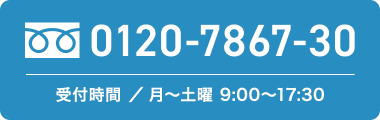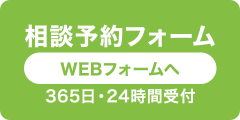死亡事故の場合の慰謝料等、保険会社に請求できる項目と、弁護士のサポートが必要な理由

監修者: 交通事故チーム主任弁護士
羽賀 倫樹 (はが ともき)
交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

- 相談者
- 交通事故で家族が亡くなった場合、どのような補償を保険会社に請求できますか?
その際は弁護士に相談した方が良いのでしょうか?
- 羽賀弁護士
- こちらのページで保険会社に請求できる項目と、弁護士に相談するべき理由について説明しますので、一緒に確認していきましょう。
- この記事でわかること
-
- 死亡慰謝料の算定基準と具体的金額
- 死亡逸失利益の計算方法について
- 葬儀費用の請求について
- 過失相殺について
- 弁護士のサポートが必要な理由
- こんな方が対象の記事です
-
- 交通事故で家族を亡くされた方
- 保険会社に適正な請求を行いたい方
- 賠償金の計算方法や請求手続きについて知りたい方
- 弁護士のサポートが必要かどうか迷っている方
はじめに

不幸にも交通事故で命を奪われてしまった場合。ご家族の皆さんは突然のことに茫然として、悲しみと怒りにうちひしがれておられると思います。命はお金に換えられるものではありません。しかし、亡くなった方が奪われたものの代償として、気持ちをしっかりと持って正当な賠償金を請求しましょう。そのためにも、何がどれだけ請求できるのか、知っておいてください。
死亡慰謝料
死亡事故の場合は、亡くなった方が一家の支柱であれば2,800万円、その他の方であれば2,000万円~2,500万円の死亡慰謝料が損害賠償として発生します。 この金額は、亡くなった本人が受け取るべきであった慰謝料と近親者分に発生する慰謝料を合計した金額とされています。 その他にも、示談交渉では困難ですが、裁判では、酒酔い運転による事故の場合等の一定の事由により慰謝料が増額された事例があります。
死亡したことにより受けた本人及び近親者の慰謝料です。
- ●一家の支柱:
- 2,800万円
- ●その他:
- 2,000〜2,500万円
なお、増減額事由は下記のとおりです。
- ●増額事由
-
- 加害者の悪性がひどい場合(刑事記録で立証)
ひき逃げ、飲酒運転、無免許運転など - 被扶養者多数(戸籍謄本で立証)
損害の発生は認められるが、具体的損害の認定困難な場合(扶養者が多数いて何らかの収入を得ていたことが認められるが、源泉徴収票などの証拠が不十分な場合など)
- 加害者の悪性がひどい場合(刑事記録で立証)
- ●減額事由
- 被害者と相続人が疎遠な場合
死亡逸失利益
死亡逸失利益 = A基礎収入 ×(100% - B生活費控除率)× C就労可能期間 に対応する Dライプニッツ係数 の算式で計算されます。それぞれの要素ごとに、必要な証拠も異なってきます。
A) 基礎収入
| 事故年または事故前年の収入となります。必要証拠は源泉徴収票となります。 | |
| 事故年または事故前年の収入となります。必要証拠は確定申告書となります。 | |
| 事故年の賃金センサスの学歴計・女子・全年齢平均賃金によります。 | |
| 原則として、賃金センサスの学歴計・全年齢平均賃金によります。ただし、上記平均賃金を得られる可能性がない場合には、学歴別平均賃金や年齢別平均賃金によります。 | |
| 学生との均衡から、(1)年齢(2)職歴(3)実収入額と賃金センサスの全年齢平均賃金との乖離の程度・原因などの諸要素を考慮して、学歴計・全年齢平均賃金、学歴別・全年齢平均賃金、学歴計・年齢別平均賃金を基礎収入とします。したがって、必要証拠としては、源泉徴収票はもちろん、職歴、仕事の内容と今後の収入の見通しなどの資料が必要となります。 | |
| 就労できる可能性や、年齢、失業前の収入の諸要素を勘案して基礎収入を決します。無職の期間が長いと、基礎収入を得る可能性がないとして、逸失利益自体が否定されますし、失業直後の場合には事故年の実収入や賃金センサスを基礎収入とされる場合もあります。 |
B) 生活費控除
被害者は亡くなったために、交通事故に遭わなければ得られるはずであった将来の収入を得ることができなくなりますので、その金額を逸失利益として請求することができます。
しかし、死亡事故の場合は、亡くなったことによって支出されなくなる生活費を損害から差し引くこととされています(「生活費控除」といいます)。
収入のうち、何割が生活費として控除されるか(「生活費控除率」といいます)は、生活の状況によって異なりますが、一家の支柱(被害者の世帯が主に被害者の収入によって生計を維持していた場合)及び女性は30%~40%、その他は50%、年少女子につき、全労働者の平均賃金を採用する場合は、生活費控除率を45%が基準とされています。 収入が少ないと、そのうち被害者の生活費として費消される割合が大きくなるため、生活費控除率も大きくなる傾向があります。
これに対して、被害者の収入によって、他の家族を扶養していた場合は、本人の生活費として費消されていた部分は少ないと考えられますから、生活費控除率も小さくなります。

生活費控除率は、生きていくために食費や住居費などの必要経費を差し引くものです。
- ●一家の支柱(働き盛りのお父さん)や女子:
- 30〜40%
- ●その他:
- 50%
一人暮らしだと経費が増える(無駄遣いが増える?)との考えから上記の違いが生まれています。
C) 就労可能期間
原則67歳までとされます。学生については、高校卒が見込まれる場合には18歳、大学卒が見込まれる場合には22歳(浪人していた等の場合は別)とされます。
なお、学生の場合には、就労可能期間は{(67歳-事故時の年齢)のライプニッツ係数-(就労開始年齢-事故時の年齢)のライプニッツ係数}と計算されます。高齢者の場合は、平均余命の2分の1と67歳までの年数のいずれか長いほうとされます。
- 例)65歳男性死亡の場合
- 平均余命の二分の一は9年(19歳÷2)、67歳までの年数は2年より、
就労可能期間は9年とされます。
D) 中間利息控除(ライプニッツ係数)
死亡逸失利益の補償を受けるということは、将来得られたであろう収入を算出して受け取るということです。しかし、まとめて受け取ることで、将来分の収入に利息が付く可能性があります。つまり、実際には算出した金額より多く受け取ってしまうことになるということです。それを調整するため、利息分を計算して予め差し引くことを、中間利息控除といいます。
この時に適用される利率については、2020年3月31日までに発生した交通事故については年5%、2020年4月1日以降に発生した交通事故については年3%を基準として、3年ごとに市場金利に合わせて変更される可能性があります。(民法404条)
これは非常に複雑な複利計算になるため、実務では「ライプニッツ係数」という係数を使って処理しています。
葬儀費用
死亡事故の場合、葬儀費用を受け取ることができます。
裁判では、概ね150万円が基準とされており、葬儀などに必要な出費と認められています。
お通夜などの費用の他、墓碑建立費やお仏壇の用意、仏具購入費などの諸経費も含まれます。それらの実際の支出額と150万円のいずれか低い方の金額が支払われるため、領収書はきちんと保管しておきましょう。
実際の葬儀では、地域の通例や参列者の人数によって、基準額を超える場合が少なくありませんが、その越えた金額を損害として裁判所が認めることはまずありません。
なお、ご遺体の搬送料は葬儀費に含まれず、別途請求できます。
過失相殺
死亡事故の場合でも、他の交通事故と同様に、保険会社から過失相殺の主張がされることがあります。つまり、被害者にも非があったのではないか、ということです。
加害者と被害者の過失割合が100対0となるのは、例えば四輪車同士の場合、「被害者が停車中に追突された」「加害者がセンターラインオーバーをしてきた」「加害者が信号無視で突っ込んできた」など、限定的な事故に限られます。そのため、死亡事故でも過失割合の検討をしなければならない事例が多数あります。
被害者が亡くなっている死亡事故の場合、過失割合を検討するには、実況見分調書などの刑事記録が特に重要な資料となります。保険会社が過失相殺の主張を持ち出した場合は、刑事記録から事故の状況を把握して、被害者に有利な事情がないか詳細に検討することが大切です。
まとめ

死亡事故は、突然のことでもあり、残されたご家族にとって非常に負担の大きい事案です。葬儀などの手配で寝る暇も無い状況の中で、不利にならないように警察の事情聴取を受け、加害者・保険会社と対応することは、精神的にも肉体的にも大きな苦痛を伴います。さらに、賠償金請求の段階になると、適正な金額の算定やさまざまな書類の準備など、一般の方には対応できないことが増えていきます。保険会社の言いなりにならず、適正な賠償金を受けるためにも、事故が発生したら一刻も早く、弁護士に相談することをお勧めします。
設立当初から、被害者側専門の法律事務所として交通事故問題の解決に取り組んできた当事務所は、被害者とご遺族の皆さんの味方となり、徹底的にサポートいたします。
更新日:2016年11月29日

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

示談金増額を目指します


ご相談者様への
お約束
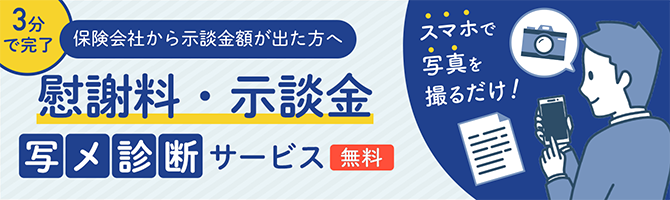
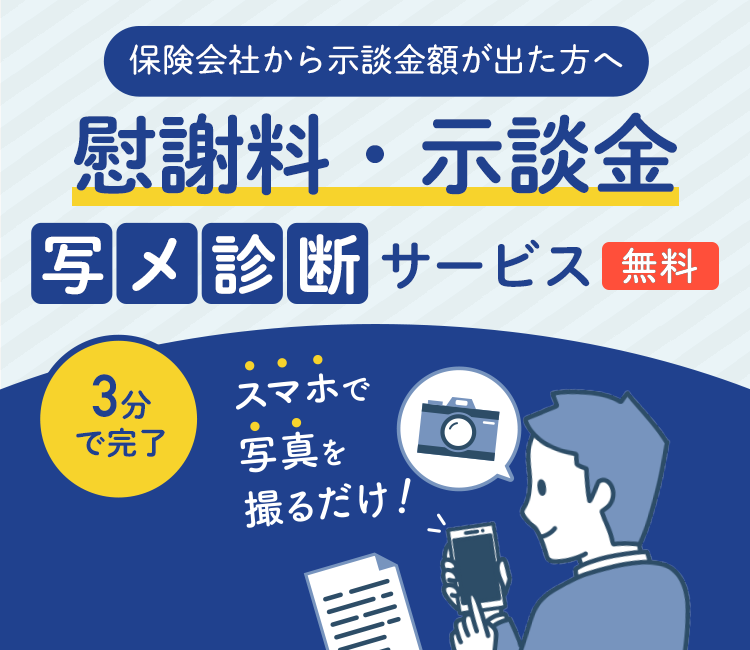


増額しなければ
弁護士費用はいただきません!
※弁護士特約の利用がない場合