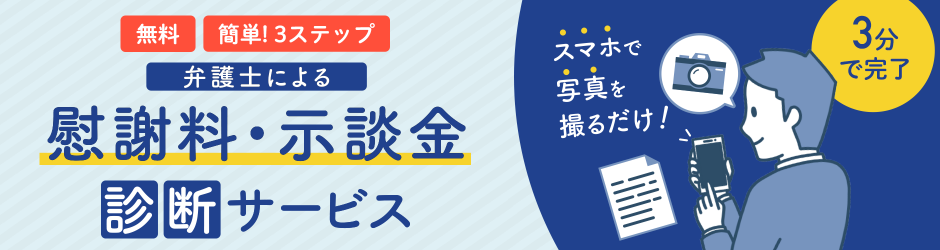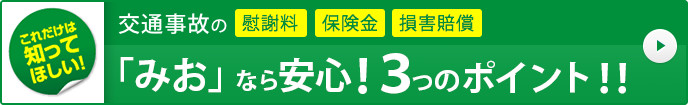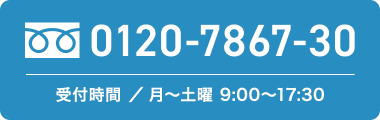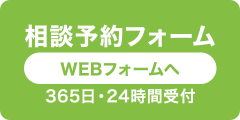将来介護費・後遺障害逸失利益と定期金賠償について

監修者: 交通事故チーム主任弁護士
羽賀 倫樹 (はが ともき)
交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

- 相談者
- 交通事故で重度後遺障害を負いました。
将来介護費用と後遺障害逸失利益について、一括での支払いと定期金方式のどちらが良いのでしょうか?
- 羽賀弁護士
- 定期金方式で支払を受けるメリットは、将来の損害分を前倒しで受け取る分の中間利息控除による減額がなくなる点です。
しかし、長期にわたって保険会社との関係を続ける必要があるなどのデメリットがあるため、ほとんどのケースで一括払い方式がとられています。
- この記事でわかること
-
- 多くのケースで定期金方式ではなく一括払い方式がとられる理由
- 後遺障害逸失利益と定期金方式に関する最高裁判所判決の内容
- 定期金賠償が認められやすくなると考えられる要素
- 定期金方式で解決した後に被害者が死亡した場合の示談金・賠償金の支払いについて
- こんな方が対象の記事です
-
- 交通事故で後遺障害が残った方やその家族の方
- 示談金の支払い方式について知りたい方
はじめに
交通事故の示談金・賠償金は、示談等による解決時に一括で支払われることがほとんどですが、重度後遺障害(遷延性意識障害・高次脳機能障害・脊髄損傷等)の場合に、介護費用を1年ごとに支払うなどの定期金方式がとられることがあります。
定期金方式のメリット・デメリット
示談金・賠償金を一括ではなく、定期金方式で支払を受けるメリットは、将来の損害分を前倒しで受け取る分の中間利息控除による減額がなくなる点です。例えば、20才代の人が交通事故で高次脳機能障害1級の後遺障害を負い、1日当たり15,000円の介護費が必要になったという事案であれば、一括支払の場合の介護費は総額約1億5000万円になります(平均余命60年、法定利息3%、ライプニッツ係数27.6756として算定)。これが、定期金方式で介護費用を60年間保険会社から受け取る場合は、総額約3億2000万円になります。金額に大きな差がありますので、一見すると定期金方式の方がいいようにも思えます。しかし、実際にはほとんどのケースで定期金方式ではなく、一括払い方式がとられています。これは、定期金方式の場合の以下のデメリット避ける必要性が高いためと思われます。
| No | 定期金方式のデメリット |
|---|---|
| ① | 示談成立後も生涯にわたり保険会社との関係を続ける必要があること |
| ② | 後遺障害の程度、賃金水準その他の損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合には、再度保険会社と交渉・裁判をする必要があり、定期金の金額が変わる可能性もあること(民事訴訟法117条1項参照) |
| ③ | 保険会社が倒産等すると、支払いを受けられなくなる可能性があること |
定期金方式には以上のようなデメリットがあるため、多くの場合、交通事故の解決の際は一括支払い方式がとられます。
後遺障害逸失利益と定期金方式
定期金方式は多くの場合、介護費用の請求の際に問題になりますが、後遺障害逸失利益でも定期金方式が認められるかが問題なります。この点について、以下の最高裁判所判決があります(読みやすくするために、最高裁判所の原文に一部改変を加えています)。
最高裁判所令和2年7月9日第一小法廷判決(民集 第74巻4号1204頁)
「(後遺障害逸失利益)は、不法行為の時から相当な時間が経過した後に逐次現実化する性質のものであり、その額の算定は、不確実、不確定な要素に関する蓋然性に基づく将来予測や擬制の下に行わざるを得ないものであるから、将来、その算定の基礎となった後遺障害の程度、賃金水準その他の事情に著しい変更が生じ、算定した損害の額と現実化した損害の額との間に大きなかい離が生ずることもあり得る。(中略)
そして、不法行為に基づく損害賠償制度は、被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し、加害者にこれを賠償させることにより、被害者が被った不利益を補塡して、不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものであり、また、損害の公平な分担を図ることをその理念とするところである。このような目的及び理念に照らすと、交通事故に起因する後遺障害による逸失利益という損害につき、将来において取得すべき利益の喪失が現実化する都度これに対応する時期にその利益に対応する定期金の支払をさせるとともに、上記かい離が生ずる場合には民訴法117条によりその是正を図ることができるようにすることが相当と認められる場合があるというべきである。
以上によれば、交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めている場合において、上記目的及び理念に照らして相当と認められるときは、同逸失利益は、定期金による賠償の対象となるものと解される。」
その上で、交通事故当時4才の子が、高次脳機能障害3級の後遺障害を負い、労働能力を全部喪失したという事案で、定期金賠償が認められました。ただし、判決で、「上記目的及び理念に照らして相当と認められるときは、同逸失利益は、定期金による賠償の対象となる」とされていますので、逸失利益について定期金賠償を求めた事案の全てで定期金賠償が認められるわけではありません。判決で考慮されている要素を見ると、被害者の年齢・労働能力喪失率・労働能力喪失期間から見て、賠償金が変更される可能性が高いほど定期金賠償が認められやすいと思われます。すなわち、被害者が若いほど、労働能力喪失率が高いほど、労働能力喪失期間が長いほど定期金賠償が認められやすいと思われます。
定期金賠償が認められやすくなると考えられる要素
- 被害者が若いか
- 労働能力喪失率が高いか
- 労働能力喪失期間が長いか
一方、上記判決の小池裕裁判官の補足意見からすると、保険会社側の債権管理等の負担、定期金賠償の方が賠償金が増える可能性があるという点は、定期金賠償を認めるか認めないかにあたって重視することは難しいと思われます。
定期金方式の賠償と被害者の死亡
示談金を一括で受け取る場合は、示談により示談金額が確定していますので、示談後に被害者の方が亡くなったとしても、示談金額に変更が生じることはありません。
一方、定期金方式の場合、示談後も保険会社からの支払が継続します。そのため、示談後に被害者の方が亡くなった場合、示談金の支払がどのようになるか問題になります。この点に関連して、以下の最高裁判所判決があります(読みやすくするために、最高裁判所の原文に一部改変を加えています)。
最高裁判所平成11年12月20日第一小法廷判決(民集 第53巻9号2038頁)
「①介護費用の賠償は、被害者において現実に支出すべき費用を補てんするものであり、判決において将来の介護費用の支払を命ずるのは、引き続き被害者の介護を必要とする蓋然性が認められるからにほかならない。ところが、被害者が死亡すれば、その時点以降の介護は不要となるのであるから、もはや介護費用の賠償を命ずべき理由はなく、その費用をなお加害者に負担させることは、被害者ないしその遺族に根拠のない利得を与える結果となり、かえって衡平の理念に反することになる。②交通事故による損害賠償請求訴訟において一時金賠償方式を採る場合には、損害は交通事故の時に一定の内容のものとして発生したと観念され、交通事故後に生じた事由によって損害の内容に消長を来さないものとされるのであるが、右のように衡平性の裏付けが欠ける場合にまで、このような法的な擬制を及ぼすことは相当ではない。③被害者死亡後の介護費用が損害に当たらないとすると、被害者が事実審の口頭弁論終結前に死亡した場合とその後に死亡した場合とで賠償すべき損害額が異なることがあり得るが、このことは被害者死亡後の介護費用を損害として認める理由になるものではない。以上によれば、交通事故の被害者が事故後に別の原因により死亡した場合には、死亡後に要したであろう介護費用を右交通事故による損害として請求することはできない。」
この事案は、将来介護費について一括払いを求めた事案であり、定期金支払いが認められた後に被害者が亡くなったという事案ではありませんが、被害者の方が亡くなった場合にそれ以降の介護費用が不要となるのは、一括払いを求めた場合でも定期金払いを求めた場合でも同じです。そのため、定期金支払いで解決した後、被害者の方が亡くなった場合、亡くなった後の介護費用は支払われなくなります。
それでは、後遺障害逸失利益が定期金賠償で認められた後に被害者の方が亡くなった場合はどうなるでしょうか。介護費用と同じく将来分の支払が受けられなくなるのでしょうか。この点について、上記の最高裁判所令和2年7月9日判決で以下の通り判断されています。
「交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害による逸失利益について一時金による賠償を求める場合における同逸失利益の額の算定に当たっては、その後に被害者が死亡したとしても、交通事故の時点で、その死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、同死亡の事実は就労可能期間の算定上考慮すべきものではないと解するのが相当である(最高裁平成5年(オ)第527号同8年4月25日第一小法廷判決・民集50巻5号1221頁、最高裁平成5年(オ)第1958号同8年5月31日第二小法廷判決・民集50巻6号1323頁参照)。上記後遺障害による逸失利益の賠償について定期金という方法による場合も、それは、交通事故の時点で発生した1個の損害賠償請求権に基づき、一時金による賠償と同一の損害を対象とするものである。そして、上記特段の事情がないのに、交通事故の被害者が事故後に死亡したことにより、賠償義務を負担する者がその義務の全部又は一部を免れ、他方被害者ないしその遺族が事故により生じた損害の塡補を受けることができなくなることは、一時金による賠償と定期金による賠償のいずれの方法によるかにかかわらず、衡平の理念に反するというべきである。したがって、上記後遺障害による逸失利益につき定期金による賠償を命ずる場合においても、その後就労可能期間の終期より前に被害者が死亡したからといって、上記特段の事情がない限り、就労可能期間の終期が被害者の死亡時となるものではない」
この判決では、後遺障害逸失利益は、将来介護費用の場合と異なり、定期金払いにより解決した後で被害者の方が亡くなった場合、これまで通りの支払が受けられることになります。ただし、亡くなった以降の後遺障害逸失利益について、民事訴訟法117条の適用または類推適用により、一括支払いに変更される可能性があります(上記最高裁判所令和2年7月9日判決の小池裕裁判官の補足意見参照)。
みお綜合法律事務所の弁護士によるまとめ

以上定期金賠償について見てきましたが、重度後遺障害の場合でも、実際には定期金賠償ではなく一括払いが選択されるケースがほとんどです。定期金賠償の方が示談金が大きくなる可能性もありますが、いずれにしても重度後遺障害の事案では示談金が大きくなり、弁護士に依頼する必要性が高いと言えます。遷延性意識障害・高次脳機能障害・脊髄損傷等の重度後遺障害が残存する場合には、できるだけ早い段階で弁護士への依頼をお勧めします。
更新日:2022年12月14日

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

示談金増額を目指します


ご相談者様への
お約束
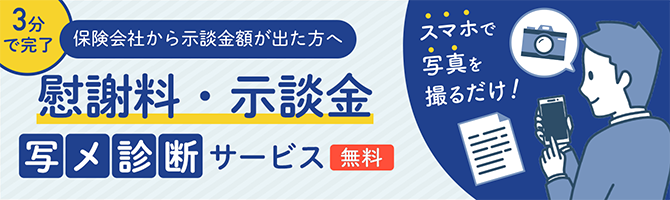
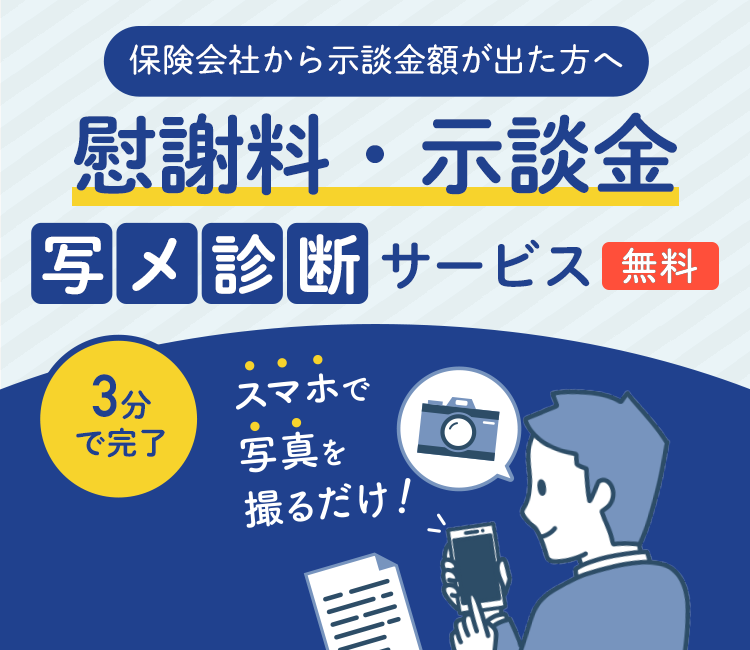


後遺障害逸失利益や介護料の請求について の記事一覧
増額しなければ
弁護士費用はいただきません!
※弁護士特約の利用がない場合
Webからのお問い合わせ・ご相談はこちら
事務所案内
- みお綜合法律事務所 大阪事務所 / JR「大阪」駅直結
- 〒530-8501 大阪市北区梅田3丁目1番3号 ノースゲートビル オフィスタワー14階(ルクア大阪すぐ近く)
TEL. 06-6348-3055 FAX. 06-6348-3056
- みお綜合法律事務所 京都駅前事務所 / JR「京都」駅から徒歩2分
- 〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町735-1 京阪京都ビル4階(京都ヨドバシすぐ近く)
TEL. 075-353-9901 FAX. 075-353-9911
- みお綜合法律事務所 神戸支店 / 阪急「神戸三宮」駅から徒歩すぐ
- 〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目3番10号 井門三宮ビル10階(神戸国際会館すぐ近く)
TEL. 078-242-3041 FAX. 078-242-3041