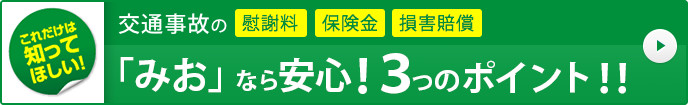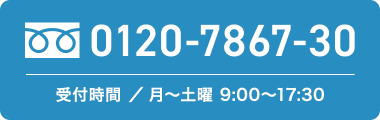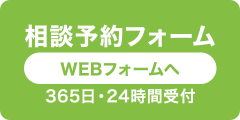交通事故における死亡逸失利益

監修者: 交通事故チーム主任弁護士
羽賀 倫樹 (はが ともき)
交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。
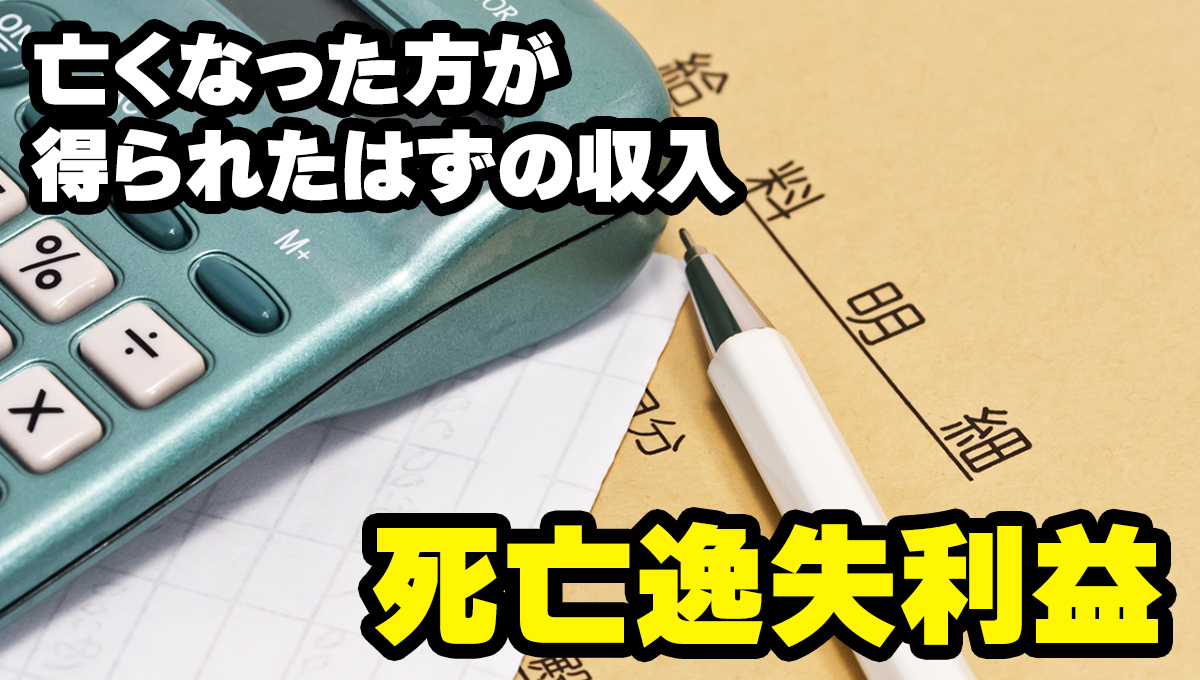
- 相談者
- 交通事故で家族が亡くなった場合、交通事故がなければ得られたはずの収入について請求することはできますか?
- 羽賀弁護士
- 交通事故で被害者の方が亡くなった場合、仕事ができなくなったことに対してや、年金が得られなくなったことに対して死亡逸失利益として賠償が認められます。
遺族の方が直接保険会社と交渉すると、逸失利益の金額が低くなってしまう可能性が高いので、弁護士に相談されることをおすすめします。
- この記事でわかること
-
- 仕事ができなくなったことに対する死亡逸失利益の計算方法
- 年金が得られなくなったことに対する死亡逸失利益の計算方法
- それぞれの計算に必要な基礎収入や生活費控除の考え方
- 労働能力喪失期間や平均余命のライプニッツ係数について
- こんな方が対象の記事です
-
- 交通事故で家族が亡くなった方
- 死亡逸失利益の計算方法について知りたい方
- 弁護士に依頼するべきか悩んでいる方
はじめに
交通事故で被害者の方が亡くなった場合、交通事故がなければ得られたはずの収入について、死亡逸失利益として賠償が認められます。死亡逸失利益には、①仕事ができなくなったことに対するもの、②年金が得られなくなったことに対するものがあります。ここでは、それぞれについての計算方法の概略について見ていきます。
仕事ができなくなったことに対する死亡逸失利益
仕事ができなくなったことに対する死亡逸失利益は、①基礎となる収入×②(1-収入に対する生活費割合)×③労働能力喪失期間のライプニッツ係数という計算式で算定されます。
①基礎となる収入
死亡逸失利益算定の基礎となる収入は、基本的に事故の前の年の年収になります。なお、以下の点等について注意が必要で、事故の前の年の収入とは異なる金額が基礎収入となるケースは多くあります。
| 仕事や年齢の状況 | 問題の内容 |
|---|---|
| 概ね30才未満の方 | 実収入ではなく、性別ごとの平均賃金や、学歴を加味した平均賃金を用いることが多くあります |
| 定年で給与の減額が見込まれる場合 | 定年後について基礎収入を下げて計算することがあります。 |
| 主婦の方の場合 | 女性平均賃金が基礎収入になります |
| 仕事もしている兼業主婦の方の場合 | 収入と女性の平均賃金の高い方を基礎収入とします。 |
| 60才以上の主婦の方の場合 | 女性の年齢別の平均賃金を基礎収入とすることがあります。 |
| 70才代・80才代の主婦の方の場合 | 女性の年齢別の平均賃金から何割か減額した金額を基礎収入とすることがあります。また、家族構成・健康状態等によっては逸失利益が認められないことがあります。 |
| 実際の収入がない幼児・児童・学生の場合 | 性別ごとの平均賃金を用いることが多いと言えます。 年少女子(概ね高校生くらいまで)の場合は、男女の平均賃金を用いることが多いと言えます。 |
| 無職の場合 | 就職の蓋然性があれば、逸失利益が認められます。その場合の基礎収入は、年齢や失業前の収入を考慮して定められますが、平均賃金や事故前の収入よりやや低い金額になることが多いと言えます。 |
概略は以上の通りですが、仕事ができなくなったことに対する死亡逸失利益の基礎となる収入の考え方は、後遺障害逸失利益の基礎収入の考え方と同じですので、以下のページを参考にしてください。
②収入に対する生活費割合(生活費控除)
被害者の方が交通事故で亡くなった場合、得られなかった収入の全額が賠償されるのではなく、生活費を支出した後で残るであろう金額について賠償が認められます。仕事ができなくなったことに対する死亡逸失利益の生活費控除は、概ね収入の30%~50%とされることが多いと言えます。詳細は、以下のページをご覧ください。
③労働能力喪失期間のライプニッツ係数
死亡逸失利益算定の際の労働能力喪失期間は、67才までか、平均余命の2分の1のいずれか長い方になります。ただし、将来得られるはずだった収入を前倒しして受け取りますので、労働能力喪失期間をそのまま当てはめるのではなく、前倒しする分の利息を控除した後の係数を当てはめることになります。例えば、27才の方が亡くなった場合、40年ではなく、23.1147という係数が使われます(2020年4月1日以降発生の事故の場合)。また、47才の方が亡くなった場合、20年ではなく、14.8775という係数が使われます。実際の年数よりかなり小さい係数となることが分かります。
ライプニッツ係数の詳細は、下記のページに記載をしています。
年金が得られなくなったことに対する死亡逸失利益
年金が得られなくなったことに対する死亡逸失利益は、①基礎となる収入×②(1-収入に対する生活費割合)×③平均余命のライプニッツ係数という計算式で算定されます。
①基礎となる収入
年金が得られなくなったことに対する逸失利益は、実際の年金額を基礎として算定されます。老齢年金・障害年金は逸失利益算定の基礎に入りますが(最高裁判所平成11年10月22日判決、東京地方裁判所平成13年12月20日判決)、加給部分や遺族年金は、逸失利益算定の基礎から除外されています(最高裁判所平成11年10月22日判決、最高裁判所平成12年11月14日判決)。受け取っている年金と拠出した保険料とのけん連関係があるかどうかで判断が分かれると考えられています。
②収入に対する生活費割合(生活費控除)
年金が得られなくなったことに対する死亡逸失利益の生活費控除は、概ね収入の40%~60%とされることが多いと言えます。仕事ができなくなったことに対する逸失利益の生活費控除よりやや控除率が高いケースが多くなります。詳細は、以下のページをご覧ください。
③平均余命のライプニッツ係数
年金が得られなくなったことに対する死亡逸失利益の対象となる期間は、平均余命までの期間です。ただし、将来得られるはずだった収入を前倒しして受け取りますので、平均余命期間をそのまま当てはめるのではなく、前倒しする分の利息を控除した後の係数を当てはめることになります。例えば、80才の方が亡くなり、あと10年年金を得られたはずという場合、10年ではなく、8.5302という係数が使われます(2020年4月1日以降発生の事故の場合)。
ライプニッツ係数の詳細は、下記のページに記載をしています。
仕事ができなくなったことに対する死亡逸失利益と、年金が得られなくなったことに対する死亡逸失利益の関係
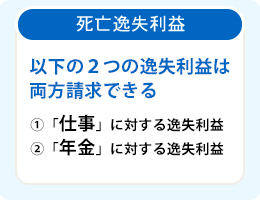
2つの死亡逸失利益は、どちらか一つしか請求できないものではなく、要件が満たされれば両方とも請求できます。例えば、定年後も仕事をして給与を受け取っており、年金も受け取っている場合や、主婦の方が年金も受け取っている場合などであれば、両方の逸失利益を請求できます。
みお綜合法律事務所の弁護士によるまとめ

以上、交通事故で被害者の方が亡くなった場合の逸失利益について見てきました。ただし、このページに記載したのは遺族の方が弁護士に交渉を依頼した場合のもので、直接保険会社と交渉となると、逸失利益の金額が低くなってしまう可能性が高いと言えます。
保険会社との示談交渉は弁護士に任せて、手続き負担を軽減するとともに、適切な賠償を求めることをお勧めします。
更新日:2022年10月28日

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

示談金増額を目指します


ご相談者様への
お約束
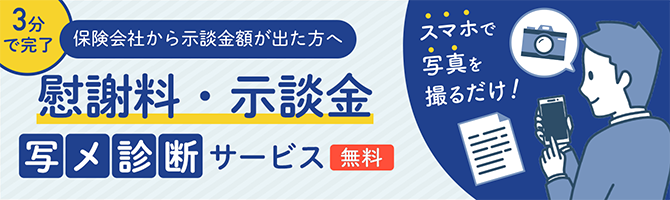
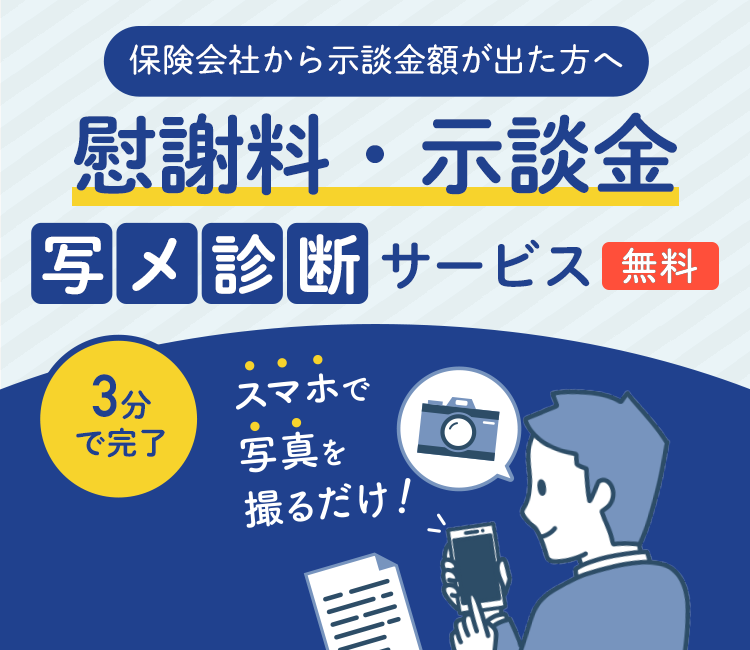


増額しなければ
弁護士費用はいただきません!
※弁護士特約の利用がない場合