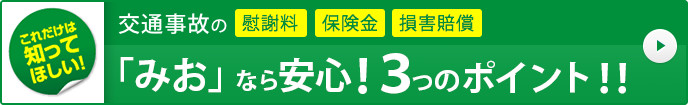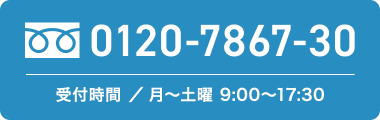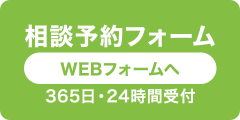交通事故における死亡逸失利益の生活費控除

監修者: 交通事故チーム主任弁護士
羽賀 倫樹 (はが ともき)
交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。
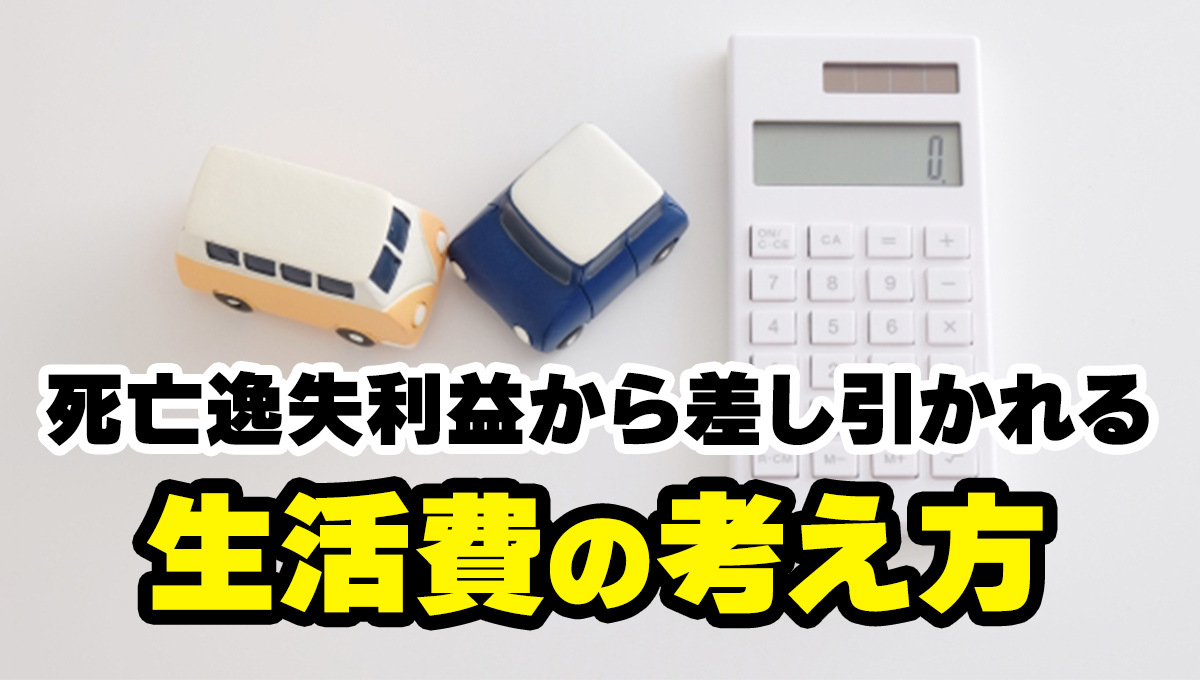
- 相談者
- 交通事故で家族が亡くなった場合、どのようにして死亡逸失利益を計算すればいいのでしょうか?
かかるはずであった生活費はどのように考慮されますか?
- 羽賀弁護士
- 死亡逸失利益は、得られるはずであった収入から生活費を控除した金額が賠償されます。
このページでは、死亡逸失利益算定の際に除外される生活費の算定方法について説明します。
- この記事でわかること
-
- 仕事ができなくなったことに対する死亡逸失利益の生活費控除の計算方法
- 年金逸失利益における生活費控除の計算方法
- 一家の支柱の方の生活費控除について
- 生活費控除の男女差について
- 収入の多寡による生活費控除率の差異について
- こんな方が対象の記事です
-
- 交通事故で家族が亡くなった方
- 死亡逸失利益の生活費控除の計算方法について知りたい方
- 弁護士に依頼するべきか悩んでいる方
はじめに
交通事故で被害者の方が亡くなった場合、交通事故がなければ得られたはずの収入が得られなくなりますので、死亡逸失利益という形の賠償が認められます。ただ、死亡逸失利益は、得られなかった収入の全額が賠償されるのではなく、生活費を支出した後で残るであろう金額について認められます。そのため、支出されるであろう生活費をどのように算定するかが問題となります。ここでは、死亡逸失利益算定の際に除外される生活費の算定方法について見ていきます。
仕事ができなくなったことに対する死亡逸失利益における生活費控除
生活費控除の概略
仕事ができなくなったことに対する死亡逸失利益算定の際の生活費控除は、亡くなった方が一家の支柱であるか、男性であるか女性であるか等によって基準となる控除率が異なります。具体的には、基礎収入から、①一家の支柱の方・女性は概ね30%~40%を控除して減額、②女子年少者(概ね高校生くらいまで)について、男女計の平均賃金を基礎収入とする場合は、概ね45%を控除して減額、③それ以外の場合は概ね50%を控除して減額して算定されます。
| 状況 | 死亡逸失利益算定の際の生活費控除 |
|---|---|
| 一家の支柱の方 | 概ね30%~40% |
| 女子年少者(概ね高校生くらいまで) | 男女計の平均賃金を基礎収入とする場合は、概ね45% |
| それ以外の場合 | 概ね50% |
一家の支柱の方の生活費控除
上記の内容を見ると、①の一家の支柱の方の生活費控除(30%~40%)と、③のその他の方生活費控除(50%)で差があります。これは、一家の支柱の方であれば、被扶養者がいるために、ご自身の生活のために収入を使う割合が低くなると考えられる一方、その他の方(一家の支柱とまでは言えない方や、一人暮らしの方等)であれば、ご自身の生活のために収入を使う割合が高くなると考えられるためです。収入のうち、実際に生活費に使う割合は人によって様々ですが、多くの事案で上記の生活費控除率が適用されており、実際の生活費割合は大きくは考慮されないのが実態です。
生活費控除の男女差
また、一家の支柱に当たらない男性の生活費控除(50%)と、女性の生活費控除(30%~40%)についても差があります。この点も、自身のために収入を使う割合という観点で説明することができるでしょうか。この点について、『2019年全国家計構造調査 家計収支に関する結果』(総務省統計局)によると、単身世帯の消費支出額は男性の方がやや大きい傾向がありますが、差はわずかですし、収入に対する割合を考えると、むしろ男性の方が消費支出割合は低くなると思われます。そうすると、自身のために収入を使う割合という観点で生活費控除の男女差を説明するのは難しそうです。
| 性別 | 死亡逸失利益算定の際の生活費控除 |
|---|---|
| 一家の支柱に当たらない男性 | 50% |
| 女性 | 30%~40% |
それでは、一家の支柱に当たらない男性の生活費控除が50%、女性の生活費控除が30%~40%という生活費控除の男女差はなぜあるのでしょうか。これは、男女の賃金差がある実態の元、死亡の際の賠償金額について大きな男女差をつけないためと考えられます。女子年少者(概ね高校生くらいまで)について、男女計の平均賃金を基礎収入とする場合は、概ね45%を控除して減額するという計算方法も、大きな男女差をつけないという考え方がベースになっていると言えます。
収入の多寡による生活費控除率の差異
収入が多いか少ないかで生活費控除率に差は出るでしょうか。生活費控除は、収入のうちかかるであろう生活費を控除するものですので、収入が高い方ほど生活費に回る割合が低く、生活費控除が低くなるようにも思えます。実際に、収入を考慮して生活費控除率を決めることもあります。一方、収入が高いにもかかわらず、高い生活費控除率を適用する事例もあります。収入が多いか少ないかは、理論的には生活費控除率に影響しそうですが、実際の運用は見えにくいというのが実態と言えるかもしれません。収入が高いにもかかわらず生活費控除率を高くした事例は、扶養利益なども考慮し、極端な高額賠償までは必要がないとの価値判断が入っている可能性もありそうです。
年金逸失利益における生活費控除
年金の受給ができなくなったことに対する死亡逸失利益について、年金は一般的に生活費に使うことが多いと言えるため、生活費分を控除して減額される割合がやや高くなる傾向があります。具体的には、実際の年金額等にもよりますが、40%~60%程度が控除され減額されることが多いと言えます。
ただ、上記『2019年全国家計構造調査 家計収支に関する結果』(総務省統計局)によると、収入のほとんどが年金収入と考えられる高齢無職単身世帯は、収入のほぼ100%が支出に充てられています。そうすると、理論上は、年金収入がよほど高くない限り、年金逸失利益は生活費控除率100%として賠償が認められないことになりそうですが、実際にはそのようにはなっておらず、40%~60%程度が控除されることが多くなっています。そのため、年金逸失利益は、生活費の実態より被害者側に有利な形で運用されていると言えます。
弁護士によるまとめ

以上、死亡逸失利益における生活費控除について見てきました。生活費控除は、その趣旨から考えると、収入のうち実際に生活費に使われる部分を基に算定するものと言えます。しかし、一家の支柱の方(30%~40%)と、③のその他の方(50%)の違いの部分から分かるように、あまり具体的に考えるのではなく、ある程度抽象化して判断されています。また、控除率の男女差・収入の多寡による影響・年金の場合の控除率を見ると、抽象化された生活費とも異なる運用となっている部分もあります。
このように、どのように生活費控除率を算定するかは、単純に生活費を考えればいいだけではなく、様々な要素を考慮して検討する必要があるものです。ご遺族の方がご自身で検討して保険会社と話をするのは難しいかもしれません。弁護士に交渉を依頼すれば、生活費控除の部分も含めて、保険会社との交渉を任せることができます。悩まれるときは、みお綜合法律事務所にご相談いただければと思います。
更新日:2021年6月9日

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

示談金増額を目指します


ご相談者様への
お約束
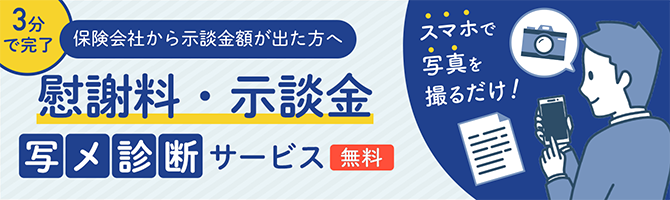
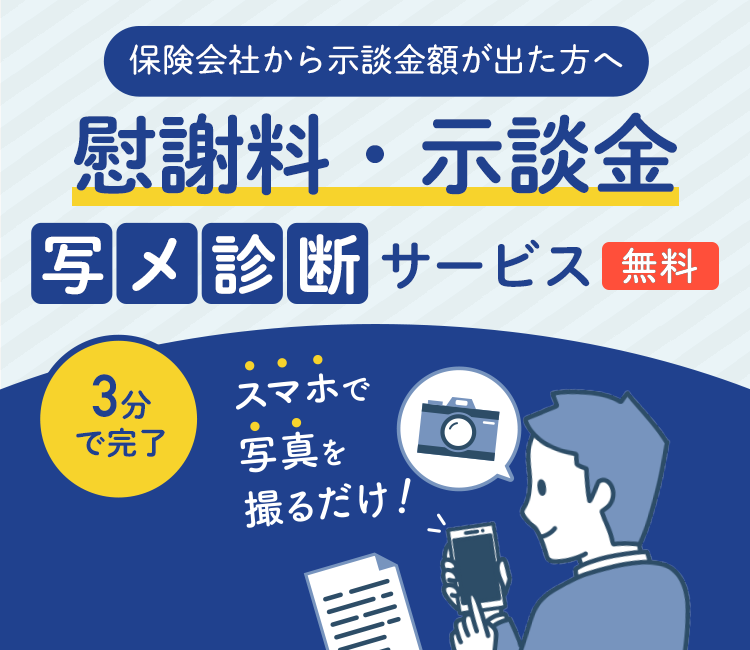


増額しなければ
弁護士費用はいただきません!
※弁護士特約の利用がない場合