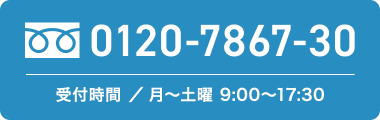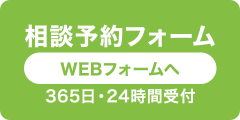自賠責保険における高次脳機能障害の有無の判断方法とは。

監修者: 交通事故チーム主任弁護士
羽賀 倫樹 (はが ともき)
交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。
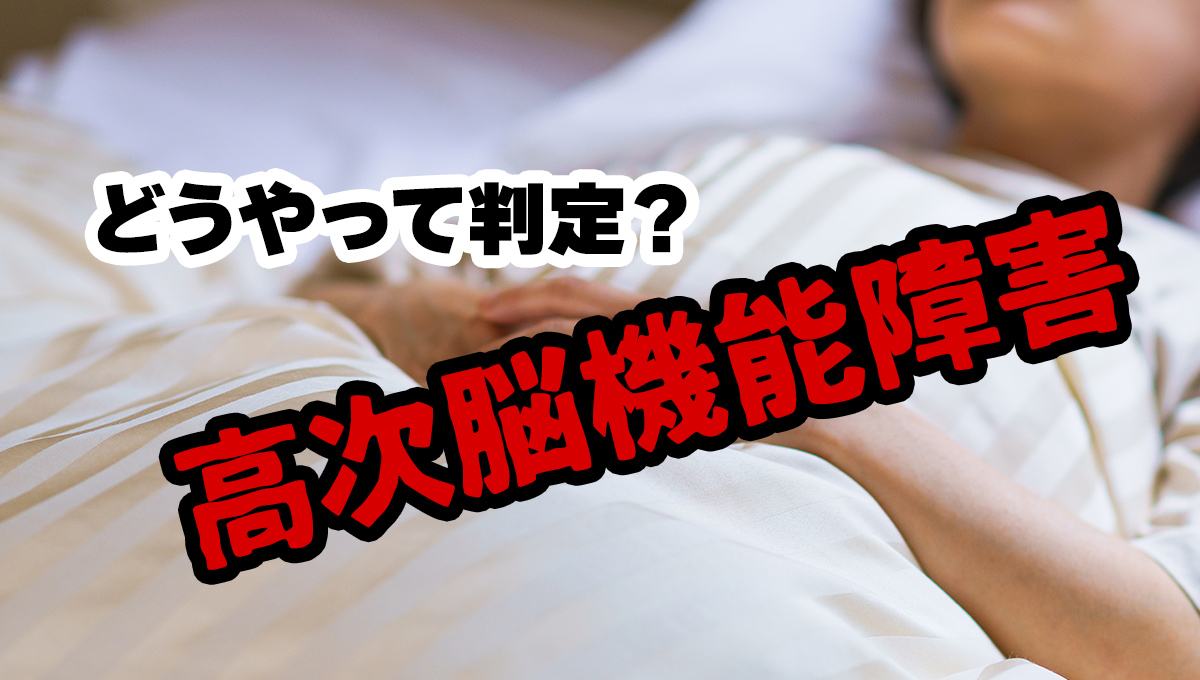
高次脳機能障害の有無はどう判断するか。【1】
■高次脳機能障害の有無
自賠責では、以下の条件に当てはまるかどうかで判断します。
| 一定時間の意識障害の継続(例えば、脳外傷直後の意識障害がおよそ6時間以上継続する症例)。かつ、 | |
| 脳挫傷、くも膜下出血、びまん性軸索損傷(びまんとは、「広範囲に散在する」という意味に解するとわかりやすいでしょう。軸策は脳の神経線維とすればイメージしやすいでしょう)などの傷病名がついていること。かつ、 | |
| 初診時の画像との比較で慢性期の画像に脳室の拡大や脳萎縮がある(PETやSPECTも所見の一つとなりえます)かつ、 | |
| 高次脳機能障害を疑わせる症状があること ・失 語…………(運動失語や感覚失語) ・失 行…………(運動失行、観念失行、着衣失行) ・失 認…………(視覚失認、半側空間無視、聴覚失認など) ・地誌障害………(よく知っている道で迷う、新しい道が覚えられないなど) ・記憶障害………(すぐ忘れる、作り話をするな等) ・遂行機能障害…(指示なしで行動できない、計画が立てられない判断できないなど) ・注意障害………(気が散りやすい、作業が長続きしない) ・人格変化………(怒りっぽい、忍耐力がないなど) |
参考①(GCS)
| ・開眼 | ・運動 | ・言語 |
|---|---|---|
| 自発的 ……… 4点 言葉による … 3点 痛みによる …… 2点 な し ………… 1点 |
自命令に従う … 6点 はらいのける … 5点 逃避的屈曲 …… 4点 異常な屈曲 ……… 3点 伸展する ………… 2点 な し …………… 1点 |
自見当識あり … 5点 錯乱状態 ……… 4点 不適当 ………… 3点 理解不能 ………… 2点 な し …………… 1点 |
参考②(JCS)
・痛みに対し無反応 …………………………………………… 300点
・痛みに対し顔をしかめたり手足を動かす ………………… 200点
・痛み刺激に対し払いのける ………………………………… 100点
・呼び鈴を繰り返して辛うじて開眼 …………………………… 30点
・簡単な命令に応じる …………………………………………… 20点
・合目的運動や言葉あるが、間違いが多い …………………… 10点
・自分の名前や生年月日をいえない ……………………………… 3点
・見当識障害がある ………………………………………………… 2点
・清明とはいえない ………………………………………………… 1点
・清 明 ……………………………………………………………… 0点
高次脳機能障害の有無はどう判断するか。【2】
■高次脳機能障害による労働能力喪失の内容
自賠責では、高次脳機能障害による労働能力喪失に関して、一人で就労ができるかという点に着目しているようです。詳しくは、次のページ「高次脳機能障害の程度(等級)は?」をご参照ください。
また、労災上では、高次脳機能を以下の4つ能力を分析して理解しています。
| 意思疎通能力(会話が成り立つか) | |
| 問題解決能力(課題を手順に従い処理できるか) | |
| 作業に関する持続力(作業に集中して途中で投げ出さないか) | |
| 社会行動能力(些細なことで激怒しないか)の各要素の支障の程度から判定します。 |
高次脳機能障害特有の症状と関連させると次のようになります(私見)。
| 意思疎通能力は、記銘・記憶力、認知力、言語力などに分けることができます(失語、失行、失認、地誌障害、記憶障害、人格変化などと関るといえます)。 ・知能テスト:MMSE、HDS-R、WAIS-Rなど ・記憶テスト:三宅式記名テスト、WMS-Rなど ・言語テスト:SLTA、WAB失語テストなど ・失行 :標準高次動作性検査 ・失認 :標準高次視知覚検査 |
|
| 問題解決能力は、理解力や判断力などに分けることができます(失行、失認、記憶障害、遂行機能障害、注意障害などに関るといえます)。 ・遂行機能テスト:BADS、WCST、FABなど |
|
| 持続力は、意欲、気分のむらなどに分けることができます(注意障害や人格変化に関るといえます)。 ・注意障害:仮名拾いテスト、数列の順唱逆唱など |
|
| 社会行動能力は、感情のコントロールや協調性や人格の変化などに分けることができます(人格変化に関ると言えます)。
A~Dのいずれも、事故前後を通じて、身近に接してきたご家族のご記憶・証言が非常に重要な意味を持ってきます。 |
次のページでは、どのような高次脳機能障害の症状が後遺障害等級の何級になるかを解説しています。
更新日:2016年11月29日

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

示談金増額を目指します


ご相談者様への
お約束
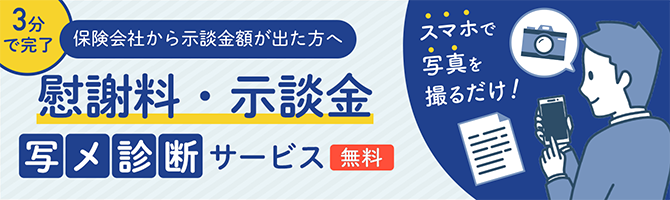
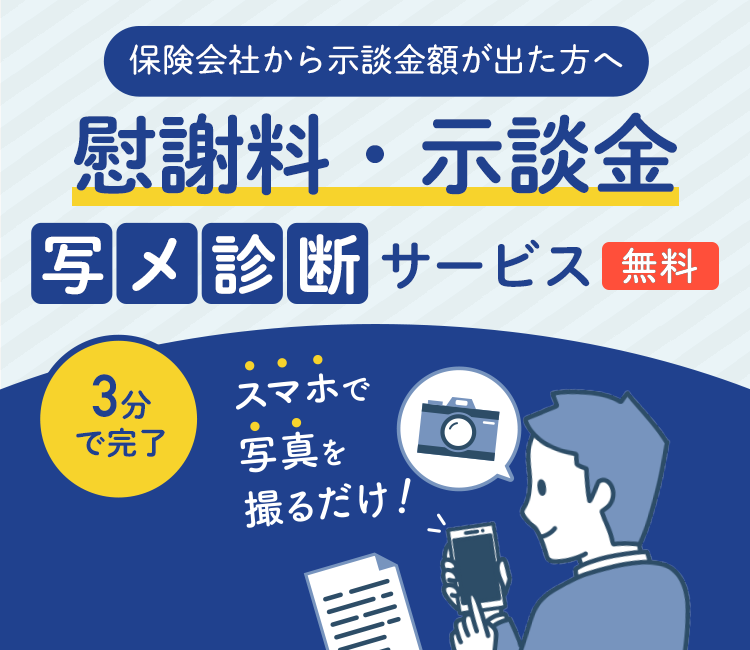


高次脳機能障害について の記事一覧
- 高次脳機能障害の症状例や交通事故による障害発生のメカニズムなど。
- 自賠責保険における高次脳機能障害の有無の判断方法とは。
- 自賠責保険における高次脳機能障害の等級の認定基準と注意点、後遺障害申請に詳しい弁護士への相談が必要な理由。
- 高次脳機能障害の症状固定時期
- 交通事故による高次脳機能障害の後遺障害等級について
- 高次脳機能障害が認定された場合の将来介護費用
- 高次脳機能障害で気をつけるべき関連症状
- 高次脳機能障害で1級が認定された場合の弁護士による示談交渉
- 高次脳機能障害で2級が認定された場合の弁護士による示談交渉
- 高次脳機能障害で3級が認定された場合の弁護士による示談交渉
- 高次脳機能障害で5級が認定された場合の弁護士による示談交渉
- 高次脳機能障害で7級が認定された場合の弁護士による示談交渉
- 高次脳機能障害で9級が認定された場合の弁護士による示談交渉
増額しなければ
弁護士費用はいただきません!
※弁護士特約の利用がない場合