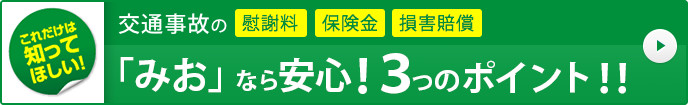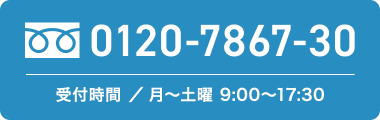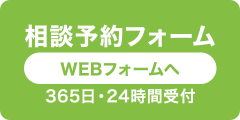交通事故の後遺障害等級認定における後遺障害診断書の重要性

監修者: 交通事故チーム主任弁護士
羽賀 倫樹 (はが ともき)
交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。
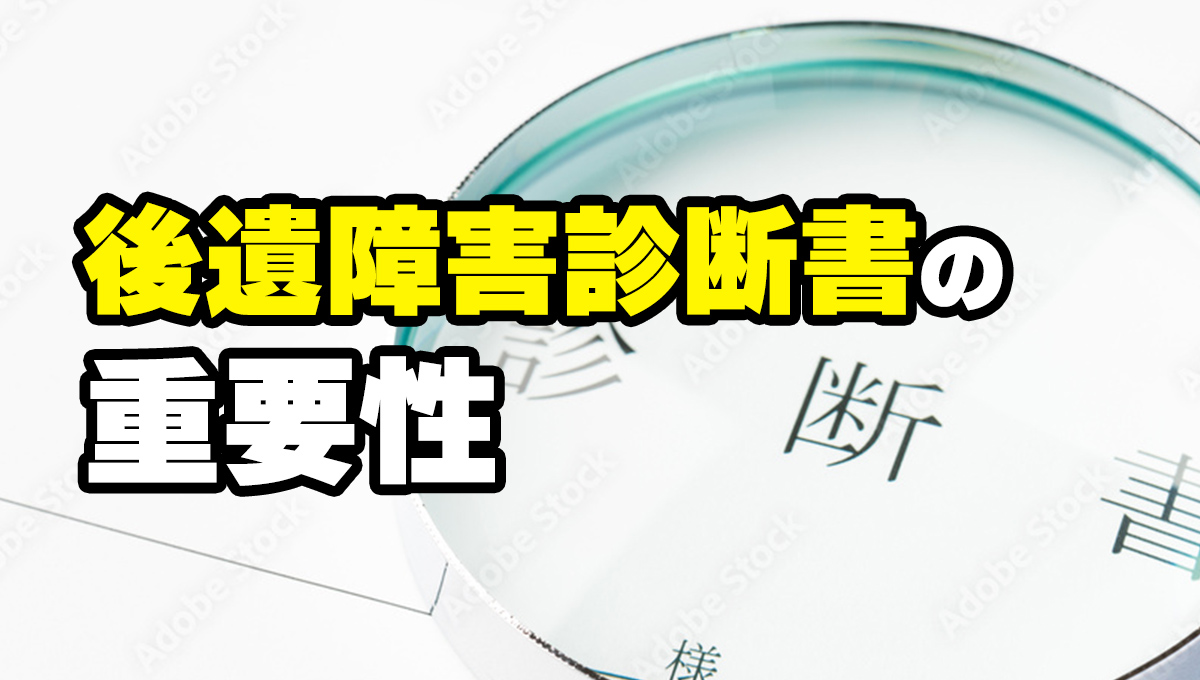
- 相談者
- 交通事故から数ヶ月経って、治療もほぼ終わりに近づいていますが、
まだ体に痛みが残っています。
適切な後遺障害等級の認定を受けるにはどうすればいいでしょうか?
- 羽賀弁護士
- 適切な後遺障害等級の認定を受けるには、後遺障害等級の認定要件を把握した上で手続きをする必要があります。
後遺障害認定要件を満たすかは、交通事故で後遺障害申請を行っている弁護士が確認する必要があります。
- この記事でわかること
-
- 後遺障害診断書の目的と重要性
- 後遺障害診断書の記載内容とその詳細
- むち打ち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)の場合に記載すべき項目
- 骨折後の痛みの場合に記載すべき項目
- 脊柱変形障害の場合に記載すべき項目
- 高次脳機能障害の場合に記載すべき項目
- 後遺障害認定を受ける過程での注意点と弁護士の役割
- こんな方が対象の記事です
-
- 交通事故に遭い「治療しても症状があまり変わらない」と感じている方
- 後遺障害等級認定のプロセスを理解したい方
- 適切な後遺障害等級の認定を受けたいと考えている方
- 交通事故に関する法的手続きや示談交渉に臨む方
はじめに
交通事故で怪我をし、しばらく治療して症状の変化が少なくなってくると、症状固定になります。症状固定時点で症状が残っていると、後遺障害等級認定が必要になります。後遺障害等級認定の際は、症状固定時の症状を記載した後遺障害診断書の記載内容を前提として、事故状況、治療時の診断書・診療報酬明細書、画像所見等を踏まえて後遺障害等級が認定されるため、後遺障害診断書にどのような記載があるかが重要になります。このページでは、後遺障害等級認定手続きにおける後遺障害診断書の重要性について見ていきます。
後遺障害診断書の記載内容
先ほど後遺障害診断書と記載しましたが、後遺障害診断書とは、症状固定時に残っている症状について主治医の先生が記載する書類です。後遺障害診断書には以下の記載項目があります。
| No | 後遺障害診断書の記載項目 |
|---|---|
| ① | 受傷日時 |
| ② | 症状固定日 |
| ③ | 入院期間 |
| ④ | 通院期間 |
| ⑤ | 傷病名 |
| ⑥ | 既存障害 |
| ⑦ | 自覚症状 |
| ⑧ | 精神・神経の障害、他覚症状及び検査結果 |
| ⑨ | 胸腹部臓器・生殖器・泌尿器の障害 |
| ⑩ | 眼球・眼瞼の障害 |
| ⑪ | 聴力と耳介の障害 |
| ⑫ | 鼻の障害 |
| ⑬ | そしゃく・言語の障害 |
| ⑭ | 醜状障害 |
| ⑮ | 脊柱の障害 |
| ⑯ | 体幹骨の変形 |
| ⑰ | 上肢・下肢および手指・足指の障害 |
| ⑱ | 障害内容の増悪・緩解の見通しなど |
①~⑦と⑱はどのような怪我であっても書く必要がある項目、⑧~⑰は怪我・後遺障害の内容によって書くべき部分が変わる項目です。
①の受傷日時は、交通事故で怪我をした日を記載します。
②の症状固定日は、主治医の先生の判断になりますが、ここの記載で保険会社が治療費・交通費・休業損害・入通院慰謝料(傷害慰謝料)等を負担する期間が決まりますので、日付が前倒しにならないように気を付ける必要があります。
また、むち打ち等の場合、治療期間が短いと後遺障害等級が認定されにくくなる場合がありますので、その意味でも注意が必要です。
③の入院期間、④の通院期間は、実際に入通院した期間を記載します。
⑤の傷病名は、主治医の先生の判断になりますが、当初の診断名や治療中に聞いた診断名と矛盾がないか等の確認が必要です。
⑥の既存障害は、後遺障害診断書に記載された後遺障害と関連する既存障害がある場合には記載が必要です。記載があると、既存障害として示談金が下がる可能性がありますし、既存障害の調査のため後遺障害等級認定まで時間がかかってしまう可能性があります。
⑦の自覚症状は、被害者の方の訴えに基づき主治医の先生が記載します。痛みやしびれなどの症状の場合、ここの記載内容で後遺障害等級が認定されるかが変わることがあります。
⑱の障害内容の増悪・緩解の見通しなどの部分は、残っている後遺障害が今後どのように変化する可能性があるか等を記載します。症状固定に至っているのが前提ですので、症状に変化がないことを記載するのが基本になりますが、記載内容によって後遺障害が認定されるかが変わることがあるため、どのような内容を記載するか注意が必要です。
怪我の状況に応じて記載すべき項目
むち打ち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)の場合
むち打ちで痛みやしびれが残っている場合、⑦自覚症状欄、⑧他覚症状及び検査結果、⑱障害内容の増悪・緩解の見通し欄の記載が重要です。
むち打ちで認定される後遺障害等級は、14級か非該当がほとんどですが、これらの記載内容によって14級が認定されたり、後遺障害等級が認定されないこともあります。認定される後遺障害等級が14級か非該当かで、示談金額が数倍変わることがあるため、後遺障害診断書の記載内容が重要であることが分かります。
骨折後の痛みの場合
骨折後の関節可動域制限がある場合は、⑰上肢・下肢および手指・足指の障害の中の関節機能障害の記載、⑱増悪緩解の見通しの欄等が重要です。
骨折部位付近の関節の可動域を記載は必須ですが、怪我をしていない側の関節可動域や、主要運動ではなく参考運動の可動域によっても認定される後遺障害等級が変わることがあります。
骨折後の関節可動域制限で12級が認定されると、交通事故前の収入・年齢・事故状況等によりますが、1000万円を超える示談金になる可能性があります。それだけに、後遺障害診断書は慎重に作成する必要があります。
脊柱変形障害の場合
圧迫骨折や破裂骨折による脊柱の変形障害の場合、⑮脊柱の障害の欄の記載が必要です。脊柱変形は、画像所見から後遺障害等級が判断される部分が大きいと言えますが、具体的症状によっては、後遺障害等級のみならず、示談交渉の際の後遺障害逸失利益の認定も見据えた記載が必要になります。
高次脳機能障害の場合
高次脳機能障害の場合、後遺障害診断書だけでなく、頭部外傷後の意識障害についての所見、神経系統の障害に関する医学的意見、日常生活状況報告の記載内容が重要です。
高次脳機能障害は、1級・2級・3級・5級・7級・9級のいずれかが認定されます。下の方の等級では2級ごとの設定になっていて、上位等級では1級ごとに慰謝料・介護料の認定が大きく変わるため、どの後遺障害等級が認定されるかで示談金額に大きな影響が出ます。それだけに、後遺障害等級に影響する上記の書面の記載内容が重要です。
弁護士によるまとめ

後遺障害診断書は、後遺障害等級認定上の重要書類で、具体的症状によって記載すべき内容も変化します。適切な後遺障害等級の認定を受けるには、後遺障害等級の認定要件を把握した上で手続きをする必要があります。主治医の先生には医学的に問題のない後遺障害診断書を作成してもらう必要がありますが、記載内容から見て後遺障害認定要件を満たすかは交通事故で後遺障害申請を行っている弁護士が確認する必要があります。
当事務所では、交通事故の被害者からの手続き依頼を数多くお受けしており、後遺障害申請も多く行っています。交通事故の手続きで後遺障害申請が必要になったという方は、みお綜合法律事務所にご相談ください。
更新日:2023年3月31日

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

示談金増額を目指します


ご相談者様への
お約束
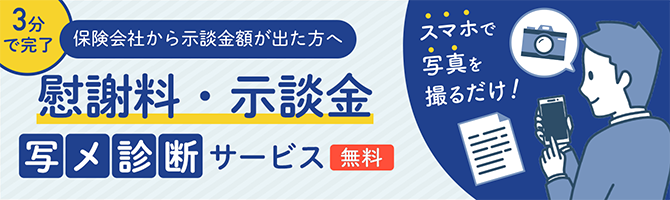
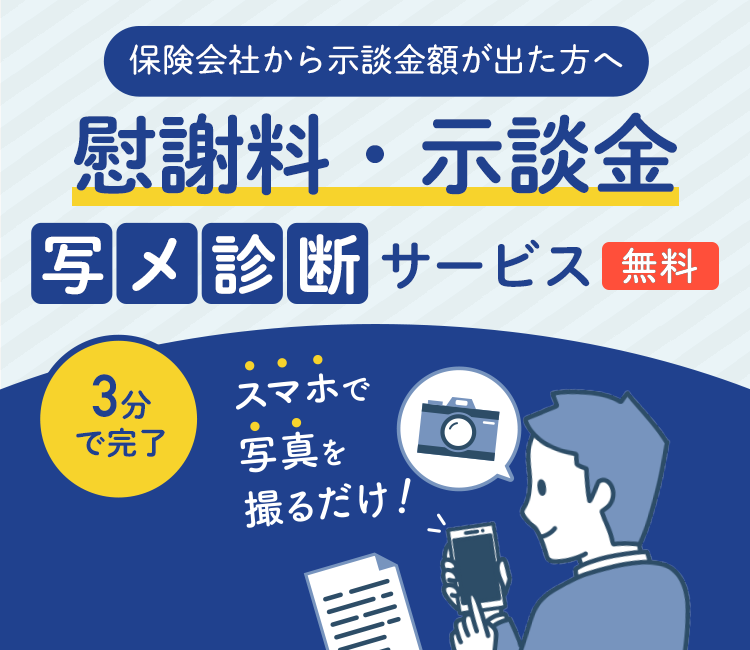


増額しなければ
弁護士費用はいただきません!
※弁護士特約の利用がない場合