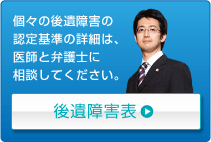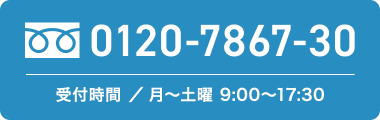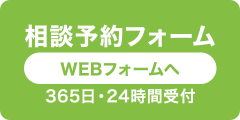後遺障害とは?分類方法、等級認定の決まりについて。

監修者: 交通事故チーム主任弁護士
羽賀 倫樹 (はが ともき)
交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

- 相談者
- 後遺障害の等級はどのように決まるのでしょうか?
- 羽賀弁護士
- 交通事故での後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令の別表に定められています。
他に「併合」「加重」「準用」という決まりもありますので、こちらのページで解説していきます。
- この記事でわかること
-
- 自動車損害賠償保障法施行令の別表に載っている後遺障害の等級や分類について
- 「併合」「加重」「準用」という決まりについて
- こんな方が対象の記事です
-
- 交通事故に遭遇し、後遺障害が残る可能性があると心配している方
- 後遺障害の認定基準について知りたい方
- 後遺障害等級の認定の「併合」「加重」「準用」について知りたい方
- 障害の残った箇所別の後遺障害等級表一覧を探している方
後遺障害とは、怪我の治療を継続しても、改善を期待することができずに残存する支障や不具合のことを言います。つまり、将来ずっと付き合っていかなければならない症状ということになります。
交通事故での後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令の別表に定められていますので、それに従って、解説します。具体的な支払額は、自動車損害賠償責任保険の保険金等及び、自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準によって定められています。
後遺障害の中身
後遺障害は、1~14級と非該当の計15の段階に分かれています。後遺障害の中身ですが、(1)身体の部位に分かれ、(2)さらに部位ごとに器質的障害か(EX:腕がなくなったなどの物理的な支障)、機能的障害(EX:腕が動かなくなったなどの身体の機能上の支障)か、などの系列に分かれます。(3)さらに、機能的障害の中でも、重い、軽いで等級を定めて順序化しています。
上記の(1)(2)(3)をまとめると、別表の通りとなります。
「併合」「加重」「準用」という決まり
後遺障害等級の認定には、「併合」「加重」「準用」という決まりもあります。
| 系列を異にする障害が2つ以上ある場合、原則として重いほうの等級によることを言います。ただし、13級以上の障害が2つ以上ある場合には1級分を、8級以上の障害が2つ以上ある場合は2級分を、5級以上の障害が2つ以上ある場合は3級分を、重い障害の等級を繰り上げます。例えば、8級と4級の系列の異なる障害がある場合、より重い4級を2級分繰上げるため、等級は併合2級となります。
もっとも、併合による等級の繰り上げについては、障害部位などによって様々な例外的取扱がありますので、障害等級に関する疑問点については弁護士と相談したほうが良いでしょう。 |
|
| 既に何らかの障害を負っていた方の障害が、事故によって更に程度が重くなった場合を言います。 賠償の対象は、事故後の等級と事故前の等級の差額となります。 |
|
| 障害等級表に載っていない障害について、障害の内容などから等級を定めることを言います。 「嗅覚脱失」や「味覚脱失」などがその例です。別表には便宜上、嗅覚脱失や味覚脱失なども記載しています。 |
次のページでは、症状固定をして後遺障害等級が出た方が必要なことを説明しています。
更新日:2016年11月29日

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

示談金増額を目指します


ご相談者様への
お約束
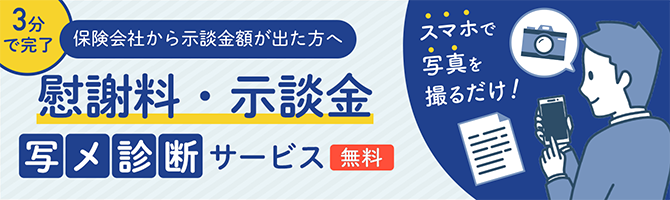
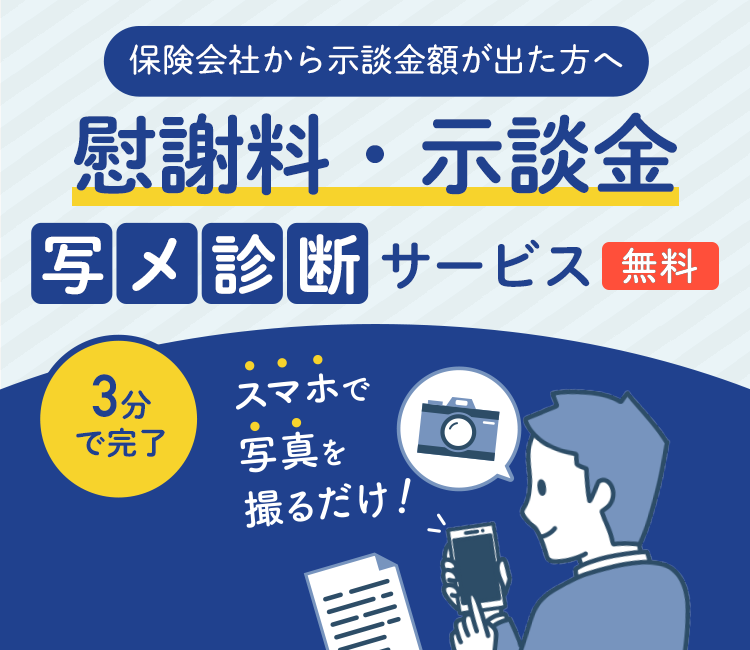


増額しなければ
弁護士費用はいただきません!
※弁護士特約の利用がない場合