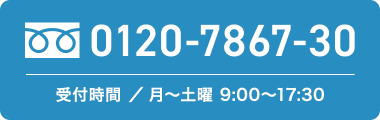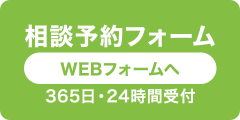脊柱変形の症状別後遺障害等級と、示談にあたって注意すること。

監修者: 交通事故チーム主任弁護士
羽賀 倫樹 (はが ともき)
交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。
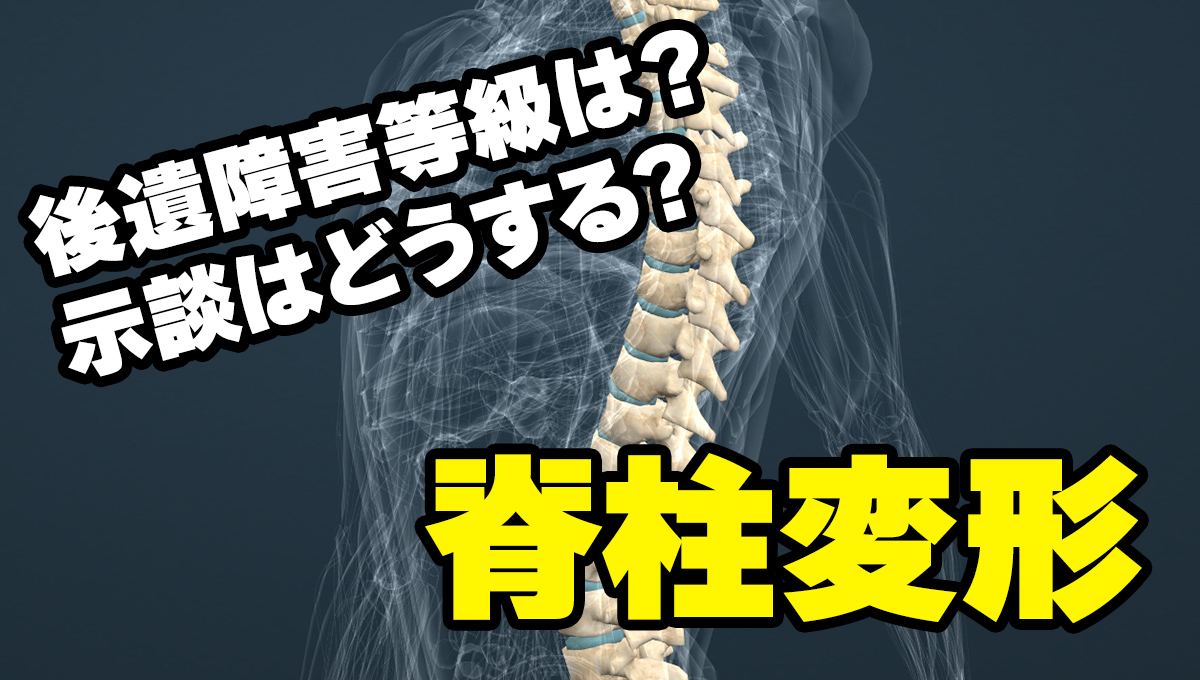
- 相談者
- 交通事故で脊柱が変形してしまった場合、後遺障害等級はどのように認定されますか?
- 羽賀弁護士
- 脊柱の変形障害は、事故の影響が大きく労働能力にも影響があり、その変形の程度により3段階の後遺障害等級が設けられています。
この記事では、脊柱の変形についてどのように後遺障害等級が認定されるのか、また示談交渉での問題点について解説します。
圧迫骨折や破裂骨折などが原因で脊柱が変形すると、日常生活に影響が出るだけでなく、労働能力にも大きな支障をきたすことがあります。
この記事では、脊柱変形の後遺障害等級についての認定基準、示談交渉での問題点について解説します。
- この記事でわかること
-
- 脊柱の変形障害に関する後遺障害等級とその基準について
- 圧迫骨折や破裂骨折による脊柱変形の検査について
- 示談交渉で問題となる労働能力の喪失について
- こんな方が対象の記事です
-
- 交通事故で脊柱に怪我を負い、後遺障害等級について知りたい方
- 脊柱の変形による逸失利益や示談金について知りたい方
脊柱変形とは?
脊柱(背骨)は、頭蓋骨から尾骨まで延長している脊椎の連続で、「脊髄を支え、可動性のある骨の枠を形成しているもの」と定義されます。脊柱が有する重要な機能として、頚部及び体幹の支持機能・保持機能並びにそれらの運動機能が挙げられます。
脊柱の変形障害とは、圧迫骨折や破裂骨折あるいは脱臼等により、脊柱が変形した状態をいいます。破裂骨折の場合、大半が脊髄損傷を伴います。
脊柱の変形障害は、前述した頚部及び体幹の支持機能・保持機能が害され、労働能力に影響を与えるものと考えられますので、その変形の程度により3段階の後遺障害等級が設けられています。
なお、仙骨及び尾骨は、解剖学上脊柱の一部とされていますが、圧迫骨折等によってそれらの骨に変形が生じても、脊柱変形に関する後遺障害が認定されることはありません。というのも、仙骨及び尾骨には、頚部及び体幹の支持機能がないからです。ただし、仙骨を含む骨盤骨の変形障害には別途後遺障害等級が設けられています。
予想される後遺障害等級
脊柱の変形障害は、変形の程度により、「著しい変形を残すもの」(6級5号)、「中程度の変形を残すもの」(8級相当)、「変形を残すもの」(11級7号)の3段階に区分されます。
以下のとおり、変形障害の後遺障害等級について6級又は8級相当と認定されるためには、画像によって圧迫骨折等が確認できる場合であることが必須要件となります。また、画像によって圧迫骨折等が確認できれば、11級の認定要件を満たすことになります(後述③★)。
① 脊柱に著しい変形を残すもの(6級5号)
★ 画像(エックス線写真、CT画像又はMRI画像)で圧迫骨折や破裂骨折あるいは脱臼などが確認できること
- 骨折等により2個以上の椎体の前方の高さの合計が、後方の椎体の高さの合計よりも、1個の椎体分以上低くなっていること
※4個の椎体の高さが、前方で11cm、後方で16cmのとき、1個当たりの椎体の高さ分(16cm÷4個=4cm)以上に、前方と後方で差が生じている(後方16cm-前方11cm=5cm)ような場合。 - 骨折等により1個以上の椎体の前方の高さが減少し、その減少した椎体前方の高さの合計が、椎体後方の高さの合計よりも、1/2個の椎体分以上低くなっており、かつ側彎度が50度以上となっていること
※★は必須要件です。
※ⅰ~ⅱのいずれかに該当すれば認定要件を満たします。
② 脊柱に中程度の変形を残すもの
★ 画像で圧迫骨折や破裂骨折あるいは脱臼等が確認できること
- 骨折等により1個以上の椎体の前方の高さの合計が、後方の椎体の高さの合計よりも、1/2個の椎体分以上低くなっていること
- 側彎度が50度以上となっていること
-
環椎(第一頚椎)または軸椎(第二頚椎)の変形・固定により次のいずれかに当てはまること
- 60度以上の回旋位となっていること
- 50度以上の屈曲位となっていること
- 60度以上の伸展位となっていること
- 側屈位となっており、矯正位(通常の頭をまっすぐにした状態)で頭蓋底部と軸椎下面の平行線の交わる角度が30度以上となっていること
※★は必須要件です。
※ⅰ~ⅲのいずれかに該当すれば認定要件を満たします。
③ 脊柱に変形を残すもの
★ 画像で圧迫骨折や破裂骨折あるいは脱臼等が確認できること
- 脊椎固定術が行われたもの(移植した骨が脊椎に吸収されたものを除く)
- 3個以上の頚椎について、椎弓切除術などの椎弓形成術を受けたもの
※★ⅰ~ⅱのいずれかに該当すれば認定要件を満たします。
示談・裁判で問題となる点
(1) 逸失利益
脊柱に変形障害が残っていても労働能力に影響を及ぼさないとして、変形障害に関する逸失利益について、損害賠償の提示金額から除かれることがあります。また、等級に見合った労働能力喪失率が提示されることは、ほとんどありません。
多くの裁判例は、何らかの形で労働能力の喪失を肯定していますが、これを否定する裁判例も少なからず存在します。また、裁判では多くの場合、労働能力喪失率が争点となります。労働能力喪失の判断にあたっては、年齢や職業、骨折の部位・程度など様々な事情が考慮されますので、個々の事案に即して適切に主張することが肝要です。
(2) 骨折等の有無
脊柱の変形障害について後遺障害等級が認定されていても、そもそも圧迫骨折等は存在しないとして、低い金額が提示されることがあります。このような場合には、すぐに泣き寝入りしてしまうのではなく、保険会社の主張根拠を精査し、骨折等の診断基準と照らし合わせたうえで、ていねいに反論を加えるべきです。
(3) 既往症
事故前から既往症があったとして、賠償額の減額を主張されることがあります。
これに対しては、事故態様や事故前の症状、通院歴があれば診療記録やレントゲンなどの画像をも参照しつつ、賠償額の減額が相当でない理由を主張立証する必要があります。
(4) MRI検査の重要性
圧迫骨折等の程度が軽微な場合、初診時に見落とされてしまうケースがあります。とくに、エックス線写真だけでは確認できなかった圧迫骨折等が、後日MRI検査で発見されるということは多々あります。
初診時に見落とされ、後日圧迫骨折等が発見されるまでの日数が長ければ長いほど、交通事故との因果関係の証明が困難となります。よって、エックス線写真では異常がないと判断されたとしても、できるだけ早期にMRI検査を受けるべきです。
(5) 解決事例
頚椎の圧迫骨折及び頚部痛により、後遺障害等級を併合10級と認定された被害者について、「そもそも骨折と診断されるべきではない」「交通事故との因果関係がない」等として労働能力の喪失が争われた事案がありました。保険会社は、医師によって作成された意見書を提示し、それらの主張の根拠としました。
これに対し、当事務所では、事故状況や治療経過等を立証しつつ、医学的な知見については主治医と面談し、その際作成していただいた意見書を提出することによって緻密に反論した結果、当初保険会社から提示された金額の2.1倍の金額(366万円→768万円)で和解することができました。
最後に
脊柱変形は、労働能力の喪失を否定する裁判例が存在するため、逸失利益の金額について争われる例が多いです。しかし、脊柱が、頚部及び体幹を支持するといった重要な機能を有する以上、これを害された場合には適切な賠償がなされる必要があります。
保険会社からの示談提案が適切な賠償金額かどうか判断する際、まずは弁護士への相談をご検討ください。
次のページでは、後遺障害慰謝料の算定の基準となる「自賠責基準」と「弁護士基準」の違いと、適正な後遺障害慰謝料を得るためのポイントを解説しています。
更新日:2016年11月29日

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

示談金増額を目指します


ご相談者様への
お約束
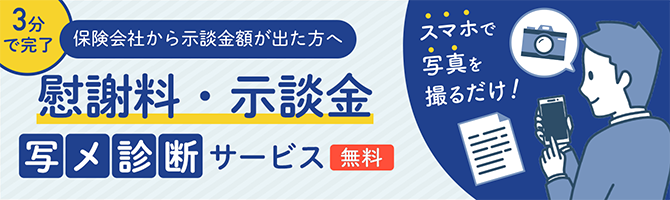
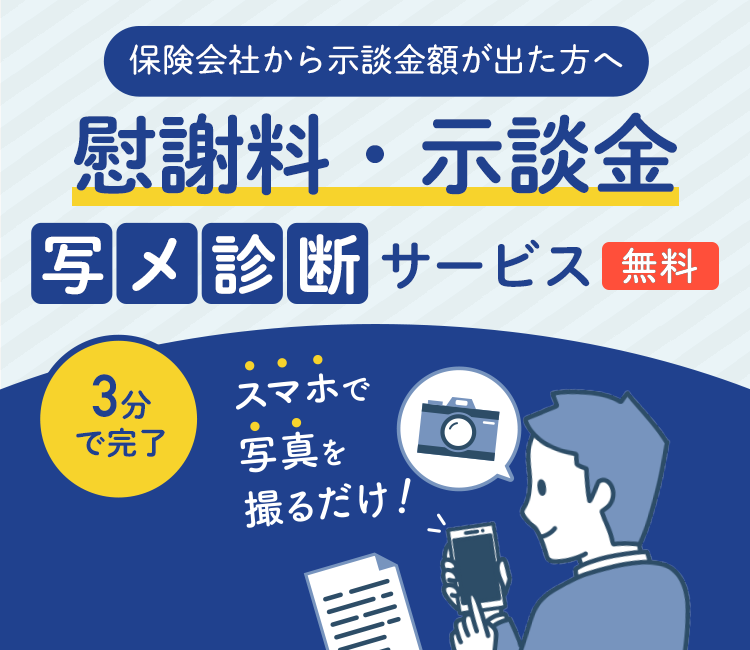


増額しなければ
弁護士費用はいただきません!
※弁護士特約の利用がない場合