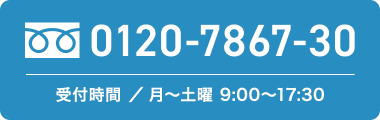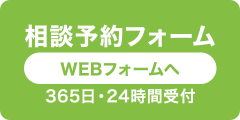交通事故による歯のケガと、後遺障害等級や損害賠償について。

監修者: 交通事故チーム主任弁護士
羽賀 倫樹 (はが ともき)
交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。
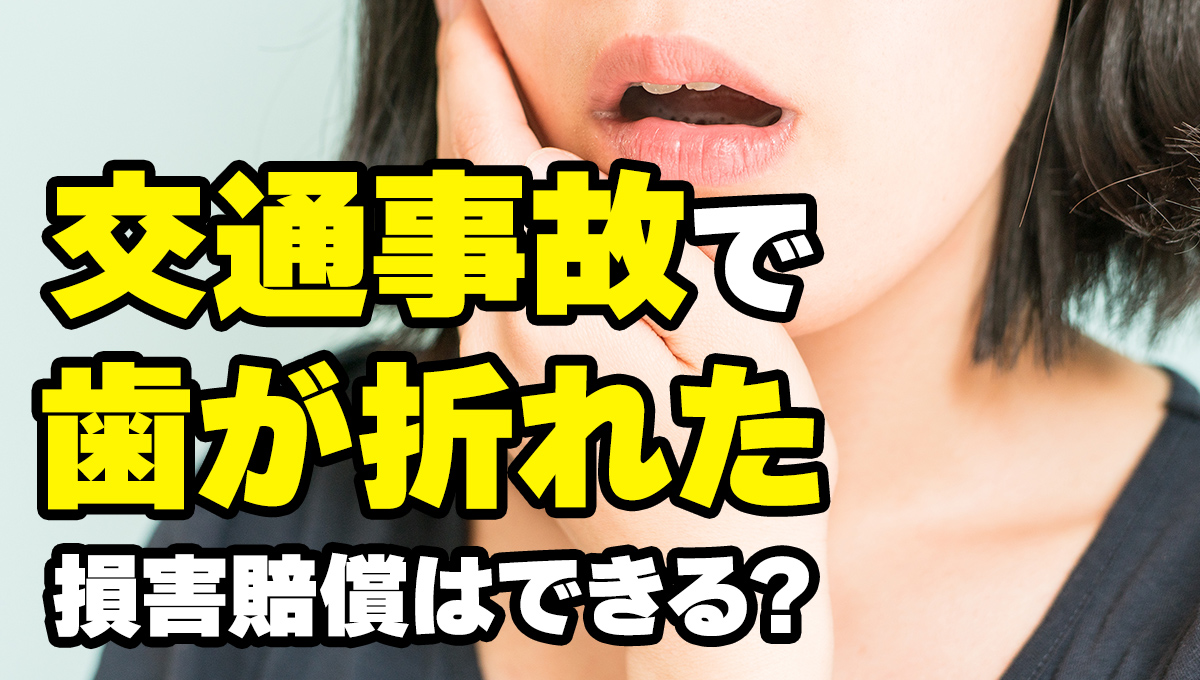
- 相談者
- 交通事故で歯を負傷した場合、どのように後遺障害等級が決まるのでしょうか?
- 羽賀弁護士
- 歯牙障害の場合、事故によって何本の歯に補綴(義歯やブリッジなど)が加えられたかによって後遺障害等級が決まります。
また、歯の損傷に関する示談交渉では、逸失利益や慰謝料がどのように認定されるかが問題になります。
一緒に詳しく見ていきましょう。
- この記事でわかること
-
- 歯牙障害の後遺障害等級とその基準
- 既存の歯の損傷や治療がある場合の「加重障害」の取り扱い
- 咀嚼や言語機能障害が伴う場合の「併合障害」の取り扱い
- 歯牙障害における逸失利益と後遺障害慰謝料
- こんな方が対象の記事です
-
- 交通事故で歯を負傷し、義歯やブリッジの装着が必要になった方
- 歯牙障害の後遺障害等級の認定基準について知りたい方
- 歯牙障害に関する示談金について知りたい方
- 弁護士に相談するか迷っている方
はじめに
事故態様や負傷箇所によっては、交通事故で歯牙(歯)を負傷する場合があります。
この場合、どういった基準で後遺障害(歯牙障害)として認定されるか、
損害賠償においてどういった問題があるかについてご紹介します。
歯牙障害とは
歯牙障害とは,一定数以上の歯に対して「歯科補綴を加えたもの」と定められていますが,
「歯科補綴を加えたもの」とは,現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補綴を意味します。
ここで,現実に歯を喪失したという場合には抜歯を含むものとされ,「著しく欠損した」とは,具体的には歯冠部(歯肉より露出している部分)の体積の4分の3以上を失った場合を指すものとされています。
そのため,①有床義歯(入れ歯)、②架橋義歯(ブリッジ)を補綴した場合における支台冠(被せものの土台)や鈎の装着歯、③ポストインレーを行うに留まった歯牙は、いずれも上記の定義を満たさないため、補綴歯数には算入しない扱いになっています。
また、喪失した歯牙が大きいか歯間に隙間があったため、喪失した歯数と義歯の数が異なる場合には、実際に喪失した歯数によって等級を認定することとされています。
歯牙障害の後遺障害等級
1)歯牙障害の後遺障害等級は、以下のように定められています。
| 等級 | 後遺障害 |
|---|---|
| 10級4号 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 11級4号 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 12級3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 13級5号 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 14級2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
このように、歯科補綴を加えられた歯数に応じて等級が定まることになりますので、認定基準としては比較的分かりやすいものといえますが、次のような点には留意しておく必要があります。
2)加重障害
交通事故に遭う前から、別の事故や虫歯の治療などのために既に歯を喪失し、あるいは著しく欠損したりして、義歯になっているような場合があります(虫歯であれば,進行して歯の根だけが残った状態であるC4クラスの場合に「著しい欠損」に該当する可能性があります)。
この場合、事故前から後遺障害等級に該当する程度の歯科補綴を加えていた人(例えば、3歯以上の歯科補綴であれば14級に該当します)が、交通事故に遭ってさらに歯科補綴を加えた結果、上位等級に該当するに至ったときは(例えば、事故で更に4歯に歯科補綴を加えた結果、合計7歯となって12級に該当することになります)、加重障害として取り扱われ、上位等級から既存の等級を控除した範囲で賠償の対象が認定されることになります(上記の例でいえば、12級から14級を控除した範囲で賠償がなされることになります)。
3)併合障害
歯牙障害が残るような交通事故であれば、顔面を負傷したことで、咀嚼又は言語機能障害が残ることも考えられます。
このような場合、咀嚼又は言語機能障害が歯牙障害以外の原因(例えば、顎骨骨折後に由来する不正な咬み合せ)に基づく場合は、併合障害として、重い方の等級又はそれを一定等級繰り上げた等級が認定されることになります。
他方、歯科補綴を行った後になお歯牙損傷に基づく咀嚼又は言語機能障害が残った場合には、各障害に関わる等級のうち、上位の等級を認定することになっています。
なお、自賠責手続の中で歯牙障害の後遺症認定を求めるためには、歯科専用の後遺障害診断書 (PDF)を主治医の先生に作成してもらう必要があります。
歯牙障害と損害賠償
| 歯牙障害による 逸失利益 |
何らかの後遺障害が認定された場合,一般には,その等級に応じた労働能力が喪失したものとして,それにより失われた利益(逸失利益)が損害として認められます。 |
|---|---|
| 歯牙障害の 後遺障害慰謝料 |
既に述べたとおり、後遺障害として歯牙障害が認定された場合でも、一般的には、労働能力に影響があるとは言い難く、逸失利益の発生を認めるのは困難なのが実情です。 |
| その他の損害 |
その他、歯牙障害が残った場合には、耐用年数が限られている場合には将来の義歯の交換費用や補綴処理費用を損害として請求する場合も考えられます。 |
まとめ

歯牙障害は、3歯以上の補綴があると14級の後遺障害が認定され、後遺障害が認定されない場合と比較して大幅に示談金額が増額になります。歯牙障害は逸失利益が認定されにくいですが、後遺障害慰謝料は認定されます。後遺障害非該当であれば0円、歯牙障害14級認定で被害者の方が弁護士に依頼しない場合概ね75万円程度、被害者の方が弁護士に依頼すれば最大110万円になります。後遺障害慰謝料を比較することで、後遺障害等級の認定を受けるメリット、弁護士に交渉を依頼するメリットがあることがよく分かります。
また、5歯以上の補綴があると13級以上の後遺障害になり、他の13級以上の後遺障害がある場合には、後遺障害等級の繰上げの対象になります。例えば、関節可動域制限で12級、歯牙障害で13級の認定の場合、併合して11級の後遺障害が認定されます。12級の場合の後遺障害慰謝料は、弁護士に依頼しない場合概ね94万円~100万円程度、弁護士に依頼した場合最大で280万円ですが、11級であれば弁護士に依頼すると最大400万円と、大幅に金額が変わってきます。
逸失利益が認められにくい歯牙障害ですが、単独認定であれ、併合認定であれ、認定されることで後遺障害慰謝料の認定額が大きく変わってきます。また、弁護士に依頼すると、後遺障害慰謝料が増額になるケースが多いと言えます。それだけに、適切な後遺障害等級の認定を受け、弁護士に示談交渉を依頼する必要性は高いと言えるでしょう。
次のページでは、後遺障害慰謝料の算定の基準となる「自賠責基準」と「弁護士基準」の違いと、適正な後遺障害慰謝料を得るためのポイントを解説しています。
更新日:2016年11月29日

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

示談金増額を目指します


ご相談者様への
お約束
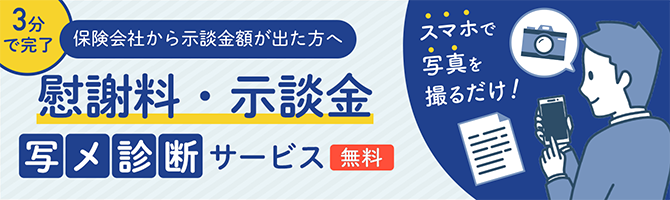
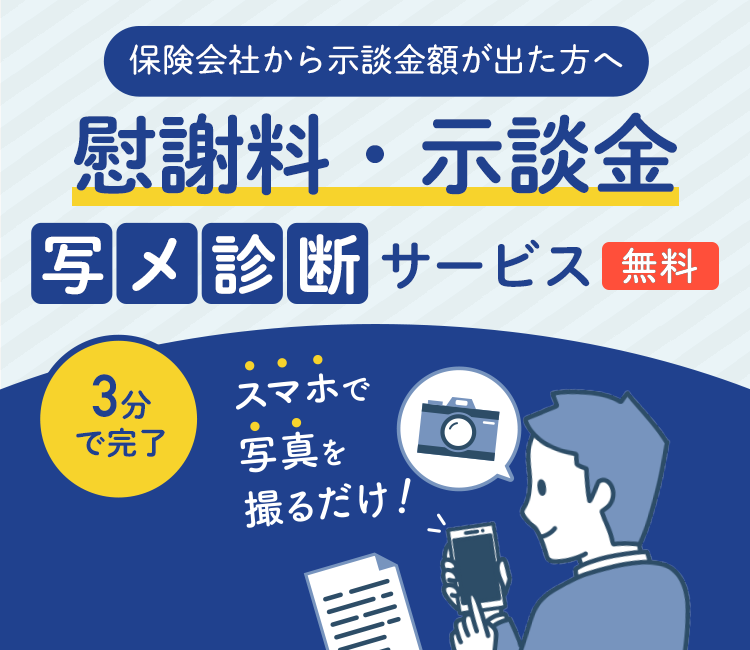


増額しなければ
弁護士費用はいただきません!
※弁護士特約の利用がない場合