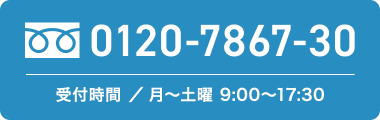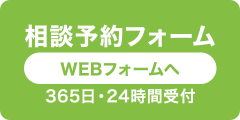交通事故による関節のケガと後遺障害、必要な検査について。

監修者: 交通事故チーム主任弁護士
羽賀 倫樹 (はが ともき)
交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。
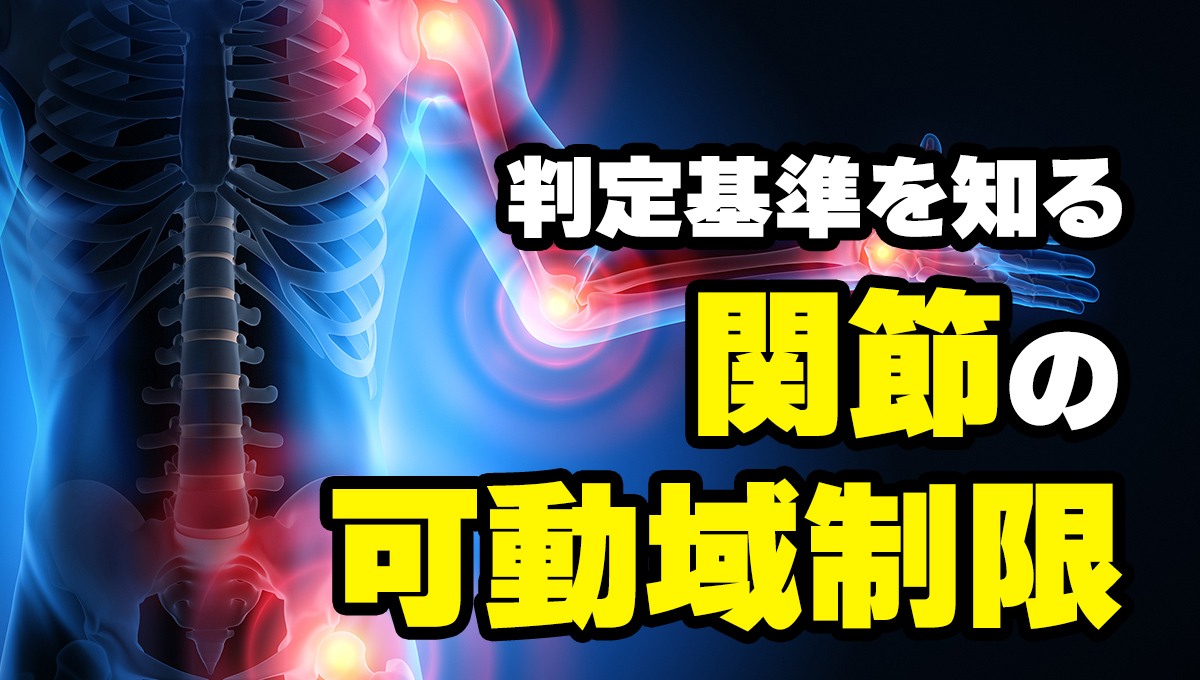
- 相談者
- 交通事故で関節付近を骨折してしまい、動かしにくくなりました。
補償や手続きはどうなるのでしょうか?
- 羽賀弁護士
- 関節の可動域制限が残ると、後遺障害等級が認定される可能性があります。
適切な補償を受けるためには、可動域の測定や弁護士による示談交渉が必要です。
こちらのページで詳しくご説明します。
このような場合、適切な補償を受けるためには、関節の可動域を正確に測定し、後遺障害等級を適切に認定してもらうことが重要です。
本記事では、関節の可動域制限に関する後遺障害の認定基準や、示談交渉での注意点、必要な検査や手続きについて解説します。
- この記事でわかること
-
- 関節の可動域制限に関する後遺障害等級の認定基準について
- 関節の機能障害で認定される等級について
- 後遺障害逸失利益の請求について
- 適正な補償を受けるために必要な検査や測定方法について
- こんな方が対象の記事です
-
- 交通事故で関節にけがを負い、可動域に制限が残った方
- 後遺障害等級の認定や可動域測定について知りたい方
- 弁護士に相談するか迷っている方
1/関節の可動域制限とは?
関節の可動域制限とは、関節の動きの障害であり、骨折、腱板損傷、半月板損傷、TFCC損傷などにともない発生することがあります。それが「どの程度の制限を生じているか?」
「障害が左右両方に生じているのか?」、「障害が一方にのみ生じているのか?」などにより、後遺障害等級が認定されることになります。
2/後遺障害の認定基準
交通事故によって、関節の可動域制限が後遺障害として残ってしまった場合、どのような後遺障害等級が認められるのでしょうか。後遺障害の等級認定基準は次のとおりです。以下では要点を絞ってご説明します。
上肢の関節の可動域制限
| 等級 | 後遺障害 |
|---|---|
| 第1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
| 第5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの |
| 第6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
| 第8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
| 第10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 第12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
(1)「上肢の用を全廃したもの」とは、3大関節(肩関節、ひじ関節及び手関節)のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれます。
(2)「関節の用を廃したもの」とは、以下のいずれかに該当するものをいいます。
- 関節が強直したもの
- 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの。「これに近い状態」とは他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下になったものをいいます。
- 人工骨頭・人工関節をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
(3)「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
- 人工骨頭・人工関節をそう入置換した関節のうち、上記2 の③以外のもの
(4)「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。
下肢の関節の可動域制限
| 等級 | 障害の程度 |
|---|---|
| 第1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
| 第5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |
| 第6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
| 第8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
| 第10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 第12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
(1)「下肢の用を全廃したもの」とは、3大関節(股関節・膝関節及び足関節)のすべてが完全強直したものをいいます。3大関節が強直したことに加え、足指前部が強直したものもこれに含まれます。
(2)「関節の用を廃したもの」とは、以下のいずれかに該当するものをいいます。
- 関節が強直したもの
- 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの。「これに近い状態」については、上肢と同様です。
- 人工骨頭や人工関節を挿入置換したもののうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
(3)「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、以下のいずれかに該当するものをいいます。
- 関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
- 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、上記(2)の③以外のもの
(4)「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。
手指の機能障害
| 等級 | 障害の程度 |
|---|---|
| 4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
| 7級7号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの |
| 8級4号 | 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの |
| 9級13号 | 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの |
| 10級7号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの |
| 12級10号 | 1手のひとさし指なか指又はくすり指の用を廃したもの |
| 13級6号 | 1手のこ指の用を廃したもの |
| 14級7号 | 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
「手指の用を廃した」とは、次の場合をいいます。
- (1)手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
- (2)中手指節関節または近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの
- (3)おや指については、橈側外転または掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているものも含む
- (4)手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの。
足指の機能障害
| 等級 | 障害の程度 |
|---|---|
| 7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
| 9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
| 11級9号 | 1足の母趾を含み2以上の足指の用を廃したもの |
| 12級12号 | 1足の母趾または他の4の足指の用を廃したもの |
| 13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
| 14級8号 | 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの |
「足指の用を廃した」とは、以下のものをいいます。
- (1)第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
- (2)第1の足指以外の足指を中節骨もしくは基節骨を切断したものまたは遠位指節間関節もしくは近位指節間関節において離断したもの
- (3)中足指節関節または近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの
「可動域制限」を理由として、後遺障害等級認定を得るためには、原則として、器質的損傷であることを明らかにすることが必要です。これは、器質的損傷がない限り、将来に渡り、障害が残存するとは考えられないためです。
3/関節可動域の測定基準
可動域の測定基準
(1)可動域の測定には、「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領」に従った測定が必要とされ、これに照らし、正しい検査がされることが重要です。
(2)具体的には、たとえば、下記のような基準が定められています。
- ア/関節可動域の比較方法
(ア)関節の機能障害の認定に際しては、障害を残す関節の可動域を測定し、原則として健側(障害が残っていない側)の可動域角度と比較することによります。
(イ)ただし、健側となるべき関節にも障害を残す場合等にあっては、参考可動域角度との比較により関節可動域の制限の程度を評価することになります。 - イ/関節運動の障害評価の区別
(ア)各関節の運動は主要運動、参考運動及びその他の運動に区別されます。
a/主要運動とは、各関節における日常の動作にとって最も重要なものをいいます。
b/関節の機能障害は、原則として主要運動の可動域の制限の程度によって評価するものです。もっとも、一定の場合には、主要運動及び参考運動の可動域制限の程度によって、評価するものとされています。(イ)各関節の主要運動と参考運動の区別は次のようなものです。
| 部位 | 主要運動 | 参考運動 |
|---|---|---|
| 肩関節 | 屈曲、外転・内転 | 伸展、外旋・内旋 |
| ひじ関節 | 屈曲・伸展 | |
| 手関節 | 屈曲・伸展 | 橈屈、尺屈 |
| 前腕 | 回内・回外 | |
| 股関節 | 屈曲・伸展、外転・内転 | 外旋・内旋 |
| ひざ関節 | 屈曲・伸展 | |
| 足関節 | 屈曲・伸展 | |
| 母指 | 屈曲・伸展、橈側外転、掌側外転 | |
| 手指及び足指 | 屈曲・伸展 |
(ウ)これらの運動のうち、原則として、屈曲と伸展のように同一面にある運動については、両者の可動域角度を合計した値をもって関節可動域の制限の程度を評価することとされています。肩関節の屈曲と伸展については、例外的に、屈曲が主要運動で伸展が参考運動であるので、それぞれの可動域制限を独立して評価することとされています。
(エ)関節可動域の測定値については、原則として、他動運動による測定値によることとされています。他動運動とは、医師などの第三者が力を加えて動かした場合をいいます。例外的に、他動運動による測定値を採用することが適切でないものについては、自動運動(自分の力で動かすこと)による測定値を参考として、障害の認定を行うとされています。たとえば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となり、他動では関節が可動するが、自動では可動できない場合がこれにあたります。
(3)可動域を測定するにあたっては、医師に角度計を使って測定をしてもらうことが重要です。角度計を使わずに大まかな記載しかしてもらえない場合、妥当な等級の認定が得られないことがあるからです。
4/後遺障害逸失利益について
保険会社が、被害者の方に示談の提案をするときには、関節の機能障害においては、労働能力喪失率や労働能力喪失期間を低く見積もって提案をするケースが多いように見受けられます。しかし、そのような場合でも、弁護士が交渉することで、労働能力喪失率や労働能力喪失期間が適正なものとなり、妥当な賠償金を得ることができることが多いといえます。交通事故で「関節を動かしにくくなった」という方で、これから後遺障害等級の認定、保険会社との示談を行うという方は、弁護士にご相談いただければと思います。
次のページでは、後遺障害慰謝料の算定の基準となる「自賠責基準」と「弁護士基準」の違いと、適正な後遺障害慰謝料を得るためのポイントを解説しています。
更新日:2016年11月29日

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

示談金増額を目指します


ご相談者様への
お約束
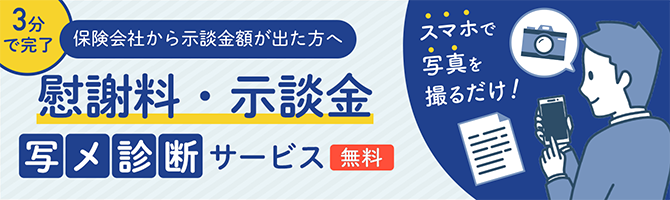
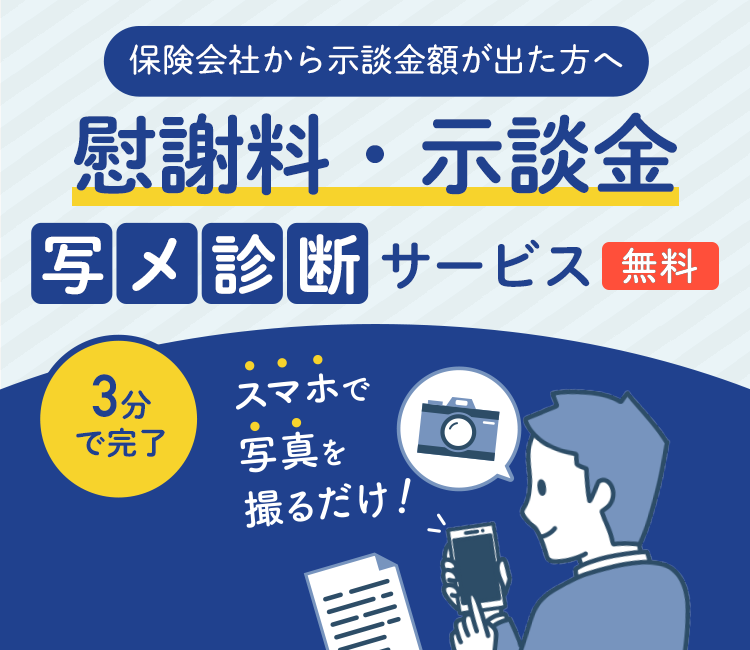


増額しなければ
弁護士費用はいただきません!
※弁護士特約の利用がない場合